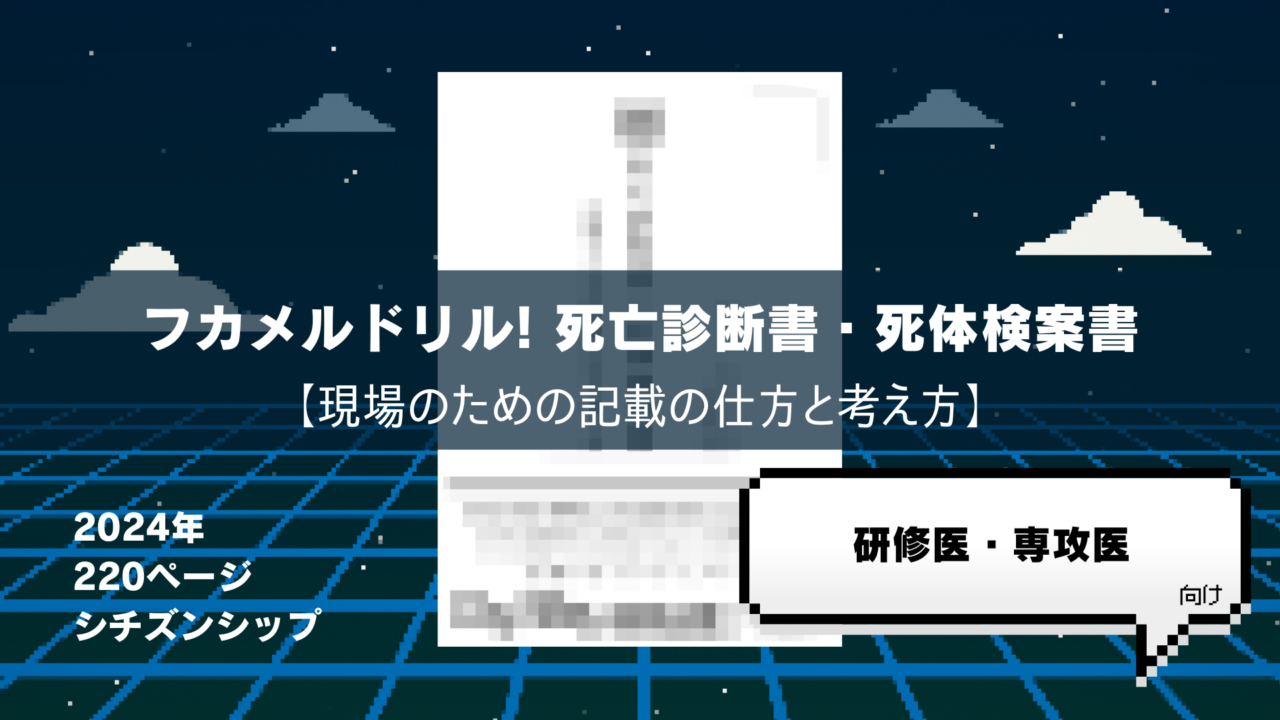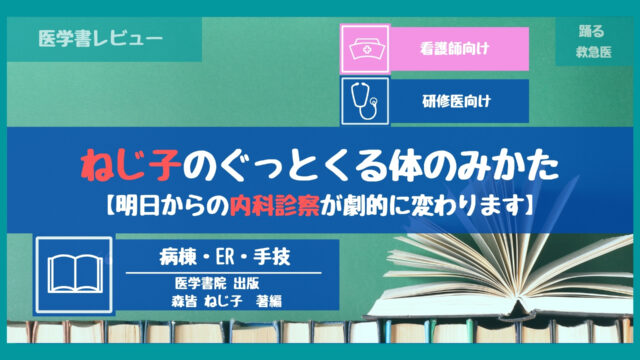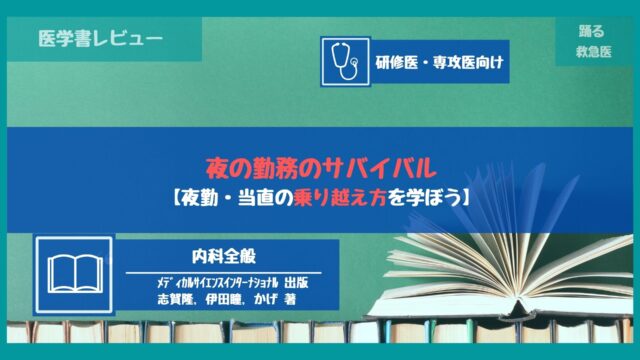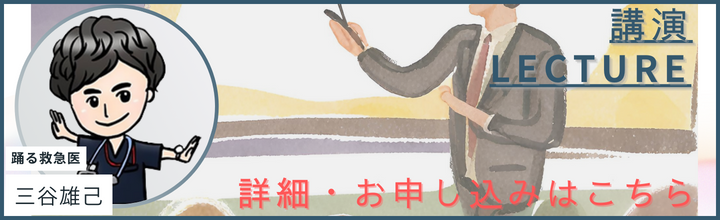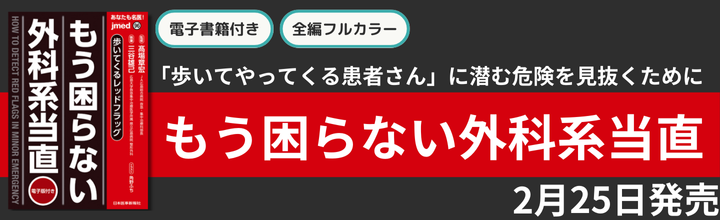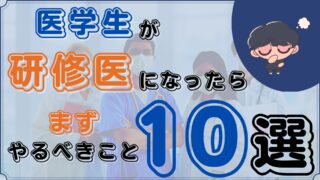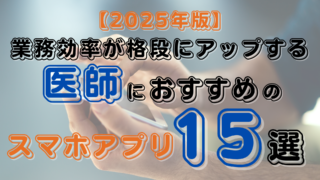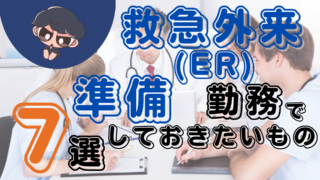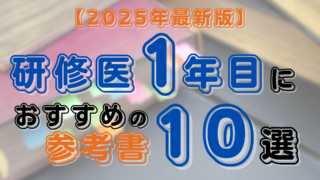死亡診断書の記載、これで合っているのかな?
異状死として届け出るべきかどうか、判断に迷う…
死亡診断書や死体検案書の記載は、医療従事者にとって避けては通れない業務の一つです。
しかし、その書式や記載ルールは意外と複雑であり、異状死届出の必要性や死因の表記、心肺停止状態をどう理解し書類上に反映するかなど、実務上の戸惑いが絶えません。
現場で働く救急医はもちろん、在宅医療や離島診療、さらには災害時の特殊な状況における死亡診断など、実は想定されるシチュエーションは非常に多岐にわたります。
私自身も救急外来で日々心肺停止の患者さんを診療する中で、死亡診断書の書き方や法的手続きについて、しばしば頭を悩ませる場面があります。
そんなとき、この一冊に出会いました。
本書を読むことで、死亡診断書や死体検案書の記載に関するストレスが激減し、どんな状況でも自信を持って対応できるスキルが身につきます!
今回、救急医療に従事するすべての方におすすめする一冊としてご紹介します👇
これからご覧いただく医学書レビューは、
これまで研修医時代に100冊以上の医学書を読み、
その中でもオススメの医学書のレビューを月5冊以上書いている
ある救急科専門医のレビューです。
医学生や研修医、各分野の初学者の気持ちが痛いほどわかるので、
是非この一冊を手に取ってみたいと思っていただけるようなレビューを心がけています!
1.本書のターゲット層と読了時間
【ターゲット層】
医師や歯科医師、看護師や医療事務スタッフ、さらに保険会社の担当者、医療過誤を扱う弁護士、自治体職員、警察関係者といった、「死亡診断書・死体検案書の内容が業務に関わるあらゆる立場の人々」
【推定読了期間】
4-6時間程度
です。
2.本書の特徴
本書は、中村 磨美先生が執筆された、
【本書の特徴】
●現場で遭遇するケーススタディを通して、現実的な対応方法を学ぶことができる
●経験に基づく実践的なヒントやエピソードが豊富に盛り込まれた「よりみち」で知識が深まる
が特徴の一冊です。
本書を読むことで学べる項目は特徴的なものをピックアップすると、このようになります👇
【本書で学べること】
●死亡診断書と死体検案書の基本的な記載方法
●異状死届出の判断基準
●海外との比較を通じた、死亡診断書に関わる柔軟な思考
これらは死亡診断書・死体検案書の内容が業務に関わる方にとっては今後どのような診療科に進んでも学んでおくべき大切な事項であると思います。
3.個人的総評
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
本書の特徴はなんと言っても、実務への直結性が高いという点でしょう。
本書は単なる教科書的な解説ではなく、救急外来や訪問診療など現場で実際に直面するケーススタディを通じて、死亡診断書や死体検案書の記載に必要なスキルを直接的に学ぶことができます。
全11症例について、「入院中の患者の死亡」「救急外来での心肺停止患者」「訪問診療・高齢者施設での看取り」「検案症例」など、多彩なシナリオを追体験することができました。
ケーススタティでは、心肺停止や老衰など、現場で曖昧になりがちな項目を具体例とともに明確に解説している点は非常に有用だと感じました。
加えて、本書は**「よりみち」の内容が豊富なことも特徴的です。**
公式マニュアルではカバーされない「現場のリアルな疑問」に答える形で、多くの「よりみち」が記載されています。
実務でつまずきやすいポイント、経験則に基づくヒントや筆者個人の感想などがふんだんに盛り込まれ、むしろ「よりみちが本文」と言えるほどの濃さです。
私自身、「あ、そういう場合はこう解釈できるのか」「老衰の定義を拡大解釈し過ぎないように気をつけよう」といった気づきが得られました。
また、付録の「死亡診断書記載チェックリスト」は、実務時の記載ミスを防ぐための具体的なツールとして非常に便利です。
手元に置いておくことで、日々の業務効率が格段に向上すると感じました。
一方で本書において注意すべきだと感じた点としては、情報量が多く「よりみち」も膨大なため、時に冗長に感じるかもしれません。
240ページというボリュームは決して短くはありません。
特に「特定の疑問に速やかに答えを得たい場合」などは、目次や索引を活用して効率的に読み進める必要があるでしょう。
また、法的根拠やガイドラインによる絶対的な裏付けを求める読者にとっては、やや物足りない部分もあるかもしれません。
個人的には、絶対的な「正解」を求めるよりも、多角的な視点や柔軟な対応策を示す本だと感じました。
逆に言えば、公式マニュアルを読んでも解決しない疑問や実務の微妙なニュアンスを補完する読み物として楽しむのが適していると感じました。
これらは本書の個人的な評価であり、しかも何様だよと言われてしまうことは重々承知ではありますが、自分は
本書は死亡診断書・死体検案書の記載に関する“現場にすぐに使える実践書”である!
と感じました。
4.おすすめの使い方・読み進め方
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
●まずは基礎編を集中して読破!
●基礎確認ドリルで知識を整理!
●実践ドリルに挑戦!
●その後は経験した症例の前後で読み直して復習!
個人的におすすめの使い方をご紹介します。
著者個人の意見としては、
まずは基礎編を集中して読み進めることで、死亡診断書・死体検案書の基本ルールを把握することが大切だと感じました。
特に初学者の方にとっては、基礎となるフォーマットを知ることができます。
その後、本書に付属する基礎確認ドリルにて、基本的な知識を確認すると良いでしょう。
短答・選択式の問題が記載されているため、国家試験感覚で楽しむことができます。
その後はケーススタディを読み進め、実戦ドリルに取り組むと良いでしょう。
この際、自分で症例を記載するつもりで解答し、解説を通じて理解を深めることがおすすめです。
そのあとは実際の症例を通じてインプットとアウトプットをたくさん経験していきましょう。
5.まとめ
【本書のまとめ】
本書は死亡診断書・死体検案書の記載に関する“現場にすぐに使える実践書”である!
まとめると、本書は死亡診断書・死体検案書の記載に悩む医療従事者にとって、必須の参考書の一つです。
救急外来や在宅医療、災害医療など、幅広い現場で役立つ知識が満載されており、初学者から経験者まで幅広い層に対応しています。
この一冊を読むことで、死亡診断書記載へのストレスが軽減され、実務スキルを向上させることができます。
多様なシナリオや「よりみち」エピソードを通じて、単なる知識ではなく、「現場での応用力」を身につけることができるでしょう。
今後の学びや業務をより良いものにしたい方には是非手にとっていただきたい一冊です◎
以下に要点や基本事項をまとめましたので、
購入する際には是非参考にしていただければ幸いです👇
【基本情報】
タイトル:フカメルドリル! 死亡診断書・死体検案書 現場のための記載の仕方と考え方
著者:中村 磨美先生
出版社:シチズンシップ
発行年月日:2024/12/20
ターゲット層は、
医師や歯科医師、看護師や医療事務スタッフ、さらに保険会社の担当者、医療過誤を扱う弁護士、自治体職員、警察関係者といった、「死亡診断書・死体検案書の内容が業務に関わるあらゆる立場の人々」
推定読了期間は
4-6時間程度
【本書の特徴】
●現場で遭遇するケーススタディを通して、現実的な対応方法を学ぶことができる
●経験に基づく実践的なヒントやエピソードが豊富に盛り込まれた「よりみち」で知識が深まる
【本書で学べること】
●死亡診断書と死体検案書の基本的な記載方法
●異状死届出の判断基準
●海外との比較を通じた、死亡診断書に関わる柔軟な思考
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
●まずは基礎編を集中して読破!
●基礎確認ドリルで知識を整理!
●実践ドリルに挑戦!
●その後は経験した症例の前後で読み直して復習!
【本書のまとめ】
本書は死亡診断書・死体検案書の記載に関する“現場にすぐに使える実践書”である!
この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は
今後も定期的に記事を更新していきますので
各種SNSの登録よろしくお願いいたします!
【公式ラインアカウント】
各種SNSでのコンテンツ配信を定期的に配信!
この中でしか見られない限定動画配信もしています◎
日々のスキマ時間に気軽に見ることができるので、興味があれば是非登録していただければ幸いです!
コチラのボタンをタップ!👇
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!