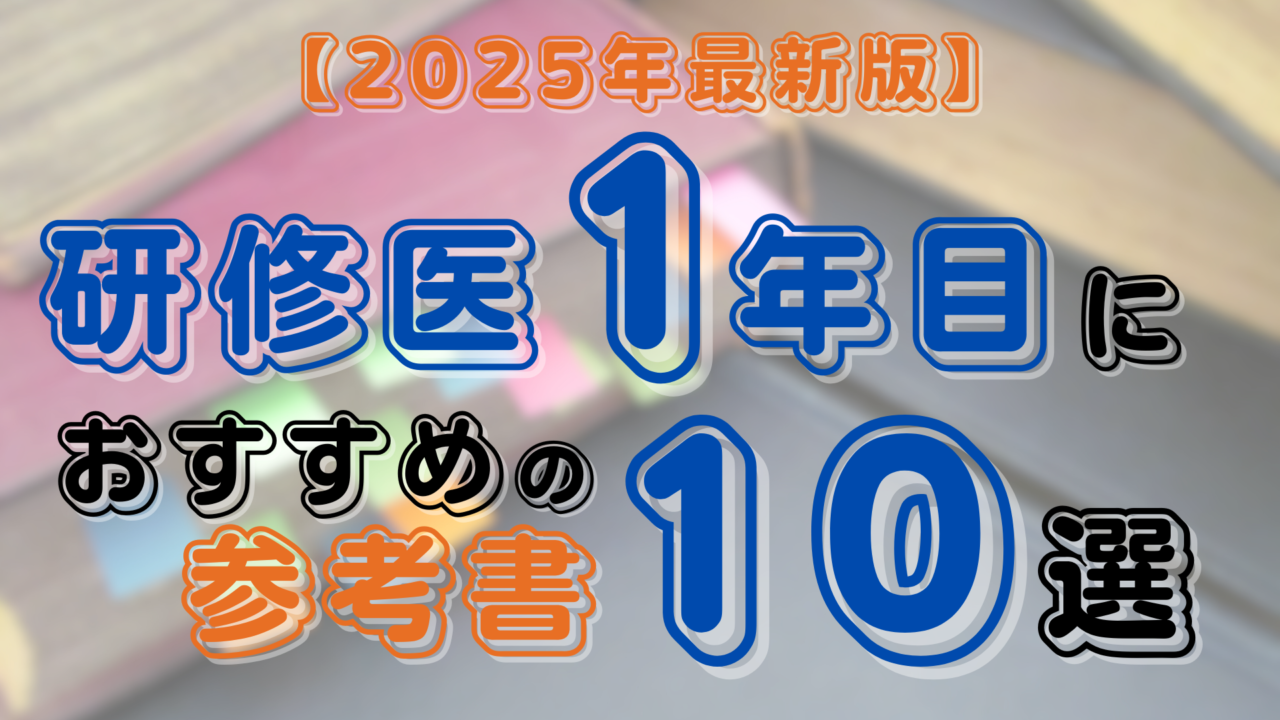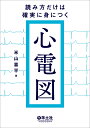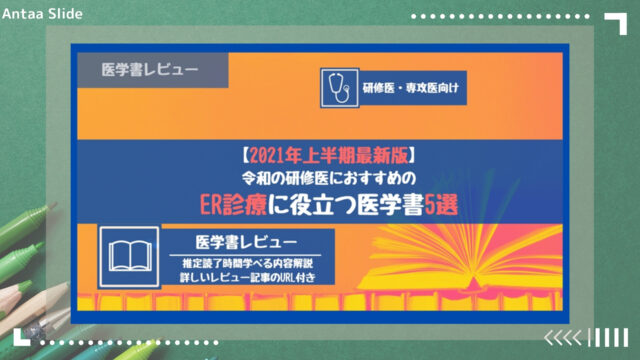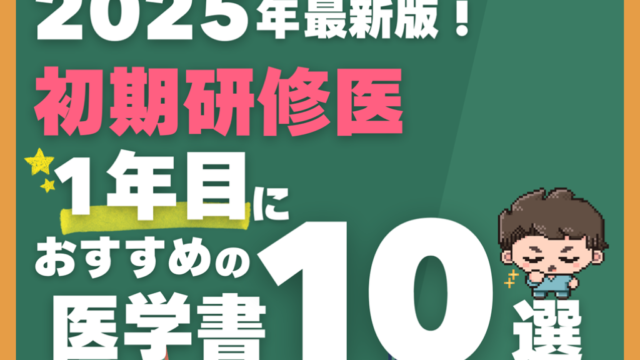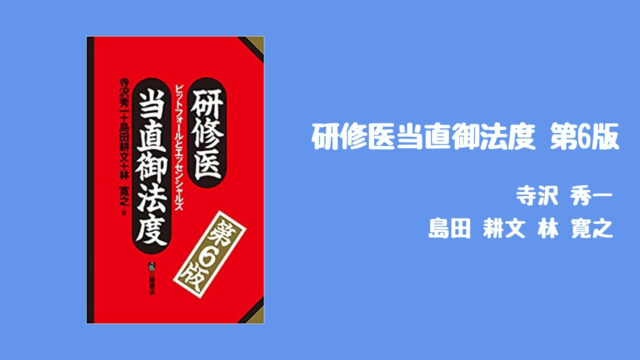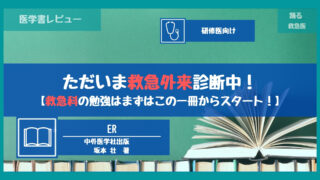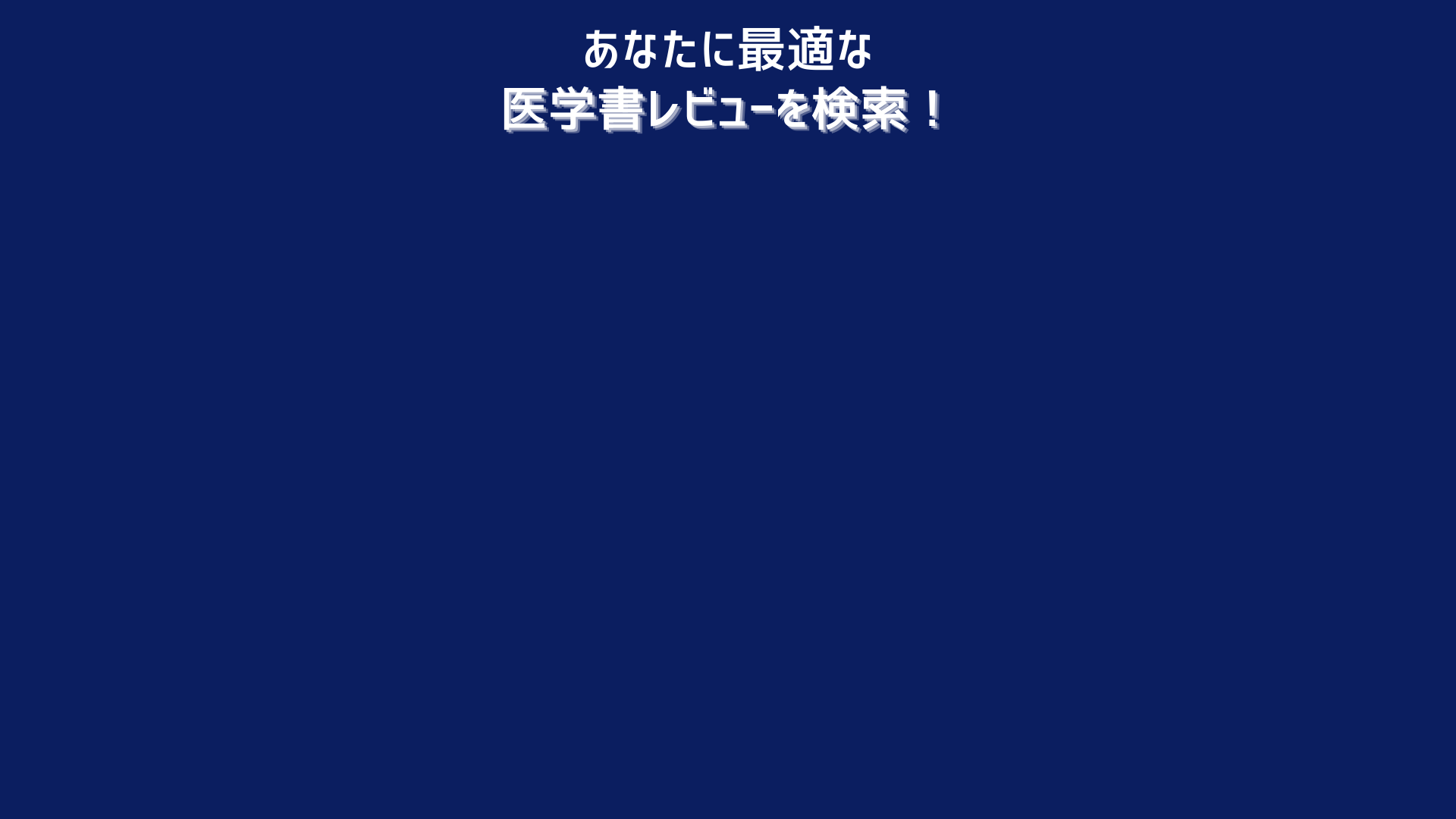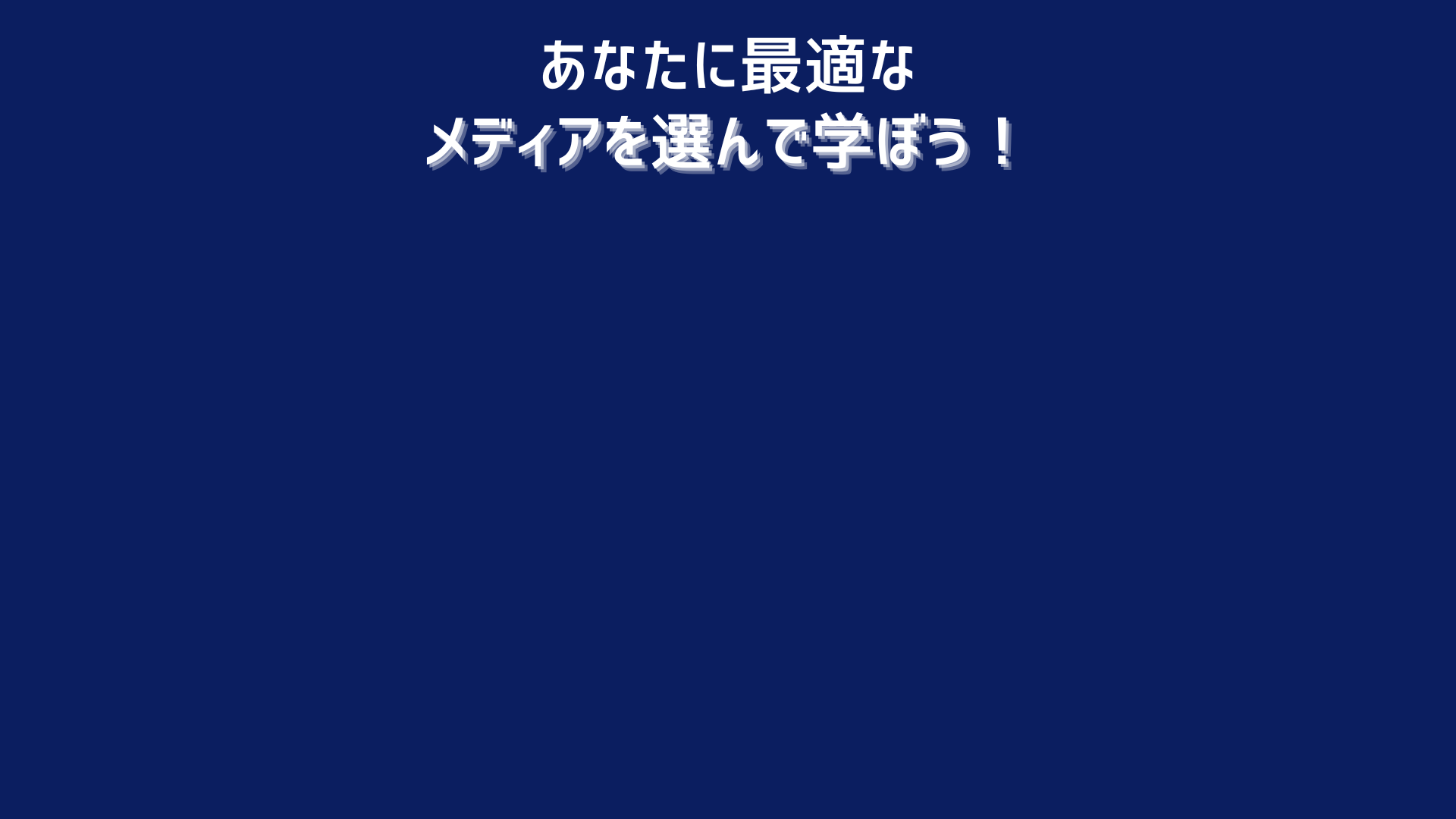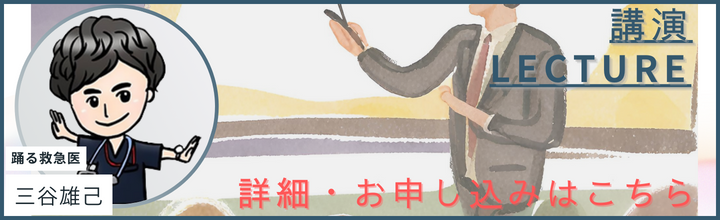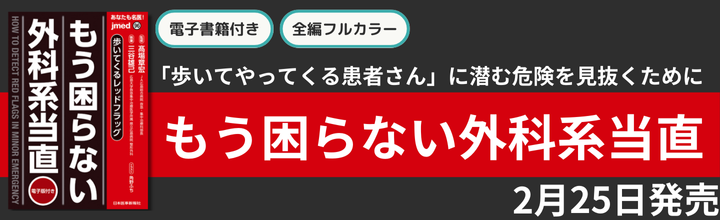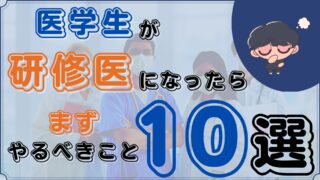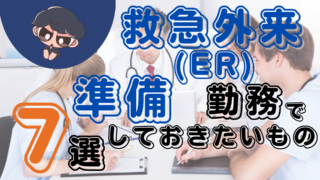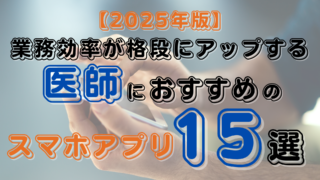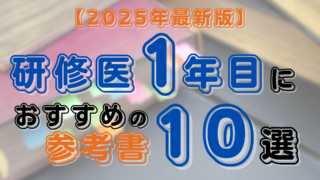医学生からいよいよ社会人として勤務し始める、初期研修医1年目。
医師として勤務していく長い人生の中でも、今後のすべての基本となる
多くのことを吸収すべき最も大切な時期であるといっても過言ではありません。
この時期に後輩や医学生の方々から必ずといっていいほど質問されるのは、
「何の参考書を買ったらいいでしょうか…?」
という質問です。
どのような参考書で勉強すべきか考える際に、まず最初に
初期研修の2年間で必ず学ぶべきことは何かを明確にしておくことが大切です。
初期研修医時代から様々な医学書を読み、救急科での後期研修3年間で数多くの初期研修医の先生方を指導する中で、自分なりに導き出したどの診療科に進んでも必ず知っておくべき、今後の医師人生において一生役に立つ知識やスキルを以下にまとめてみました👇
①内科診療
②救急外来診療
③病棟管理・病棟指示
④カルテ記載
⑤輸液管理
⑥感染症診療・抗菌薬
⑦手技(気管挿管・静脈路確保・CVC留置など)
⑧血液ガス
⑨エコー(超音波検査)
⑩心電図
つまり上記のような要素は、将来どの診療科に行っても絶対必要となるものであり、これら要素を効率的かつ簡単に学ぶことができる書籍を選択するのが大切です。
今回はこれらの要素を学ぶのに最適な、初期研修医1年目が研修医生活中に読むべき個人的におすすめしたい選りすぐりの医学書を10冊をご紹介します!
自施設に加えて全国の研修医へヒアリングして選び抜いた、とっておきの10冊です📚
これから何の参考書を使って勉強をしようか迷っている方は、是非参考にしてみていただければ幸いです◎
今後の研修医生活で必ず必要になる参考書ばかりなので、早いうちに揃えておくのもおすすめです。
勉強熱心な先生方には特におすすめですので、是非チェックしてみてください!
これからご覧いただく医学書レビューは、
これまで研修医時代に100冊以上の医学書を読み、
その中でもオススメの医学書のレビューを定期的に執筆している
若手救急医のレビューです。
医学生や研修医、各分野の初学者の気持ちが痛いほどわかるので、
是非この一冊を手に取ってみたいと思っていただけるようなレビューを書くよう
心がけています!
1.『内科レジデントの鉄則』
あまりに有名な参考書であり、冗談抜きに日本中の研修医は必ず一冊持っているのではないかという大ベストセラーです。
もはや説明不要かもしれませんが、内科診療について学ぶことのできる教科書としては間違いなくこの本をおすすめします!
酸素療法や血糖管理、ステロイド換算など必ず学んでおくべき基本事項が網羅されています。
医学生が研修医になるまでに、まず最初に通読すべき医学書として最も適した一冊と言えるでしょう。
【基本情報】
タイトル:内科レジデントの鉄則 第3版
著者:聖路加国際病院内科チーフレジデント (編集)
出版社:医学書院
発行年月日:2018/4/16
【分野】
内科 総合内科 プライマリケア
【タイプ】
症例・疾患ベース
【ターゲット層】
国家試験終了後の医学生~初期研修医1年目(特に前半)
【推定読了期間】
10-12時間程度
【本書で学べること】
●現場でよく遭遇する症候の鑑別
例)入院中の患者の発熱で見逃しやすい、想起すべき原因(7つ)は?
●内科救急の具体的初期対応
例)高Kの重症度判定と具体的な治療薬(投与量も含め)は?
●悩ましい入院患者の管理
例)refeedingで想定すべき電解質異常は?
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
※Amazon評価:
【本書のまとめ】
研修医が良い臨床研修を始める上で必須の参考書の一つである!
本書は初期研修医必携の内科分野の初学書である!

2.『当直ハンドブック ver.2』
胸痛の患者さんが搬送されるけど、まず何から鑑別をつけようか…?
溺水の患者さんが5分後に搬送される…何を気をつけて初期診療を行うべきだろう…?
急性膵炎っぽいと診断はつけられたけど、コンサルトする前にまとめるべき重症度分類のチェック、専門科が来るまでに対応しておかないといけないことって何だっけ…?
私自身、研修医時代はもちろん、救急外来での当直勤務は今も悩むことや確認しなければならないことばかりです。
これらの悩みを解消するために、さっと情報を参照できるハンドブックはとても有用ですよね。
これまで、様々なハンドブックを読み漁ってきた医学書オタクの自分ですが、今回はこれまで読んだ中で最も使いやすくおすすめのハンドブックに出会ったのでご紹介させていただきます◎
本書を読むことで
今後当直業務中のストレスは激減します!
また、それぞれの疾患に対するポイントをすぐに把握できるので、専門科にコンサルトする時に良好なコミュニケーションを取ることができます!
以前の改定前(2021年初版)の、あくまで個人的な印象ではありますが、
電解質異常のアセスメントや対応についてはひとくくりにされており、当直中に対応するシチュエーションが多い割には少し心もとない印象を受けていました。
しかし、電解質領域や外傷領域などの内容拡充のため、初版刊行後、毎年という短かいインターバルで改訂を繰り返しており、それらの不安は払拭されています!
ハンドブック系では手薄となりやすい、中毒診療まで詳しく解説されており、非常に網羅性の高い一冊へとさらに進化していると感じました…!
もちろん今年度の2025年度verにも改訂されており、まさに隙のない救急ハンドブックであると言えますね◎
今回当直業務中に必ず携帯しておくべき一冊として自分が自信をもっておすすめするのがこちらです👇
【基本情報】
タイトル:当直ハンドブック 2025
著者:志賀隆(編集)
出版社:中外医学社
発行年月日:2024/12/27
【ターゲット層】
初期研修医から後期研修医
【本書の種類】
辞書系・ハンドブック
【推定読了期間】
10-12時間程度
【本書の特徴】
●当直や救急外来で経験するイベントや臨床疑問を2分で解決し対処できることを目標に構成されている
●総勢504ページにわたる情報が網羅的に掲載されており、当直中のほぼすべての疑問に関して対応できる
●それぞれのシチュエーションに対応できるようになるのはもちろん、最新の医学知識や思考回路をエビデンスに基づいて掲載いただいているので、それぞれの症候や疾患に対応したあとの振り返りやフィードバックにも利用できる
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
●どこにそれぞれの分野が掲載されているは把握するため、目次を参考にしながらまず通読!
●実用的、すぐに参照できるようにしておきたい箇所については付箋などを貼って整理しておく
●その後は当直帯に経験するシチュエーションの前後で読み直して復習!
【本書のまとめ】
●本書は当直業務にあたる研修医・若手医師必携の一冊である!
3.『病棟指示と頻用薬の使い方 決定版』
研修医になって初めてぶつかる大きな壁の一つが、病棟患者さんへの指示出しです。
病棟管理は研修医が周りのスタッフから信頼を得られるかを試される試練の場なので、
まずはこの病棟指示という国家試験でまったく勉強したことのない概念を学ばなければならないのです。
病棟指示や管理はそれぞれの施設や先生によって異なりますが、ほぼルーティンのように対応されることも多く、これまで研修医時代も含め、自分自身も体系的に教わることがありませんでした…。そんなもやもやを抱えていた時に出会ったのがこの一冊です。
こちらの書籍は、以前2021年5月号のレジデントノート特集として組まれていた企画を、よりパワーアップして完全版として書籍にした一冊となっております。
前作のレジデントノートももちろん素晴らしかったのですが、この書籍はあらゆる点でさらに進化しており、衝撃を受けました…!
本書を読むことで、今後の医師人生を通じての病棟指示や管理のストレスは激減します!
タイトル:病棟指示と頻用薬の使い方 決定版〜持参薬対応や病棟でのマイナートラブル対処まで、意外と教わらない一生使える知識の詰め合わせ
著者:松原知康・宮崎紀樹
出版社:羊土社
発行年月日:2022年12月13日
【ターゲット層】
初期研修医から後期研修医
【本書の種類】
通読系・目次系
【推定読了期間】
7-8時間程度
【本書で学べること】
●発熱時や頻脈・徐脈時、SpO2低下時などよくあるシチュエーションでの適切な投薬・処置の指示の出し方と、Dr.Callされたときの考え方・動き方
●持参薬継続の意思決定やマイナートラブルなど、病棟管理で悩みやすい項目の具体的な評価方法やアクションプラン
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
●これまで悩んだ病棟管理を思い出しながらまず通読
●病棟管理で悩んだ時はいつでも参照しながら実践で学んでいく
●本書を用いて後輩が入力してくれた病棟指示や入院管理をフィードバックすることで学びを深める
【本書のまとめ】
本書は今後医師人生の中で一生必要な、病棟管理や指示の知識についてわかりやすく学べる研修医必読の一冊である!

病棟指示は医学的知識もとても重要ですが、看護師さんとのコミュニケーションツールでもあり、なかなかそのコツを医学知識を学ぶためだけの書籍で学ぶのは困難です…。
コミュニケーションなど、国家試験勉強やでは身に付けられない…
臨床現場の「見えない壁」を乗り越えるための本が誕生しました!
興味がある方は下のボタンをクリックして、試し読みしてみてくださいね!

4.『「型」が身につくカルテの書き方』
●S欄とO欄、どちらに書けばいいのかが決まってない。。
●O欄は検査結果のコピーしかない。。
●A欄は指導医の意見を転記しているだけ。。
あなたはいわゆるこんな、ダメカルテを記載してしまってはいませんか?
空手の型のように、カルテの書き方にも型があるのです!
働き始めの初期研修医がまず参考にすべき、おすすめのカルテの入門書がこちらの一冊です。
本書を読んだ後のカルテ記載は、体系的にまとまったカルテの作成を意識できるので、
医学生や初期研修医など早い段階での通読をおすすめします。
【基本情報】
タイトル:「型」が身につくカルテの書き方
著者:佐藤 健太
出版社:医学書院
発行年月日:2015/4/9
【ターゲット層】
医学生から後期研修医
【推定読了期間】
4-5時間程度
【学べること】
「基本の型」の部では、SOAP形式や問題リストなどのカルテ記載法のエッセンスを習得することができ、合わせて医師らしい思考過程を身につけられる
どんな場面でも実践することが出来る「応用の型」の部であり、外来・救急などセッティング別のカルテ記載法を習得できる
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
【まとめ】
本書はカルテ記載を学ぶ初学者にとって必須の参考書の一つである!
5.『レジデントのためのこれだけ輸液』
初期研修医になった瞬間、点滴の選択や流量を日々オーダーするという業務が発生します。
輸液分野に関しては国家試験で総論的な内容は学ぶことはあっても、
具体的な思考過程を学ぶことは少ないのが現状です。
そんな研修医にとっての鬼門の一つである輸液分野の初めに読むべき一冊として自分が自信をもっておすすめするのがこちらの一冊です。
初学者へ圧倒的に寄り添った解説や構成となっており、明日からの点滴オーダーが難なく行うことができる基礎について、無理なく学ぶことができます!
タイトル:レジデントのための これだけ輸液
著者:佐藤 弘明
出版社:日本医事新報社
発行年月日:2020/6/29
【ターゲット層】
医学生から後期研修医・看護師
【推定読了期間】
8-10時間程度
【本書で学べること】
- 細胞外とは何か。なぜわざわざそのような名称を使うのか。
- GI療法の仕組みは何か。
- 輸液の量を決定する際に必要な項目である代謝水とは何か。
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
※Amazon評価:
【本書のまとめ】
本書は輸液を学ぶ初学者にとって必須の参考書の一つである!
本書は今後、研修医が初めに輸液について学ぶ医学書のゴールドスタンダードになる!
番外編?.『みんなの救命救急科』
僭越ながら、初期研修医など救急診療の初学者に徹底的に寄り添った書籍を先日出版させていただきましたので、ご紹介させてください…笑
当書籍のメインテーマは救急診療の基本、ABCDアプローチです。
どのような救急診療の書籍でも語られているテーマではありますが、総論的な解説で終えられていることも多く、読んでみても結局現場でどうしたらいいのか、よくわからないと感じたことはありませんか?
様々なハンドブックや参考書を勉強しても、なぜか上手に救急診療ができないのは、
ABCD アプローチを真に理解できていないからなのです。
救急外来診療、院内急変に苦手意識を持つみなさまが、少しでも自信をもって診療にあたることができるよう、願いを込めて執筆しました。
是非一度、ご一読していただけると嬉しいです!
【基本情報】
タイトル:みんなの救命救急科
著者:三谷雄己 監修:志馬伸朗
出版社:中外医学社
発行年月日:2022/10/27
【ターゲット層】
医学生から後期研修医
【推定読了期間】
9-10時間程度
【学べること】
ABCDアプローチのための思考回路を徹底的に掘り下げ、手技を実践するためのテクニックをわかりやすいイラストと文書で解説
経験の少ないスタッフが救命の現場で判断に迷いやすいポイント
心肺蘇生や血液ガス分析など、ABCDアプローチを実践する上で欠かすことのできない救急診療の知識
【まとめ】
本書は救急診療の原則である”ABCDアプローチ”を学ぶのに最適な一冊である
6.『感染症プラチナマニュアル Ver.9 2024-2025』
この患者さん尿路感染症みたいだけど、具体的にどれくらいの治療期間が必要なんだっけ…?
レボフロキサシンを使うように上級医に指導されたけど、使用する上で注意すべきことって何だっけ…?
これら悩みを解消しようとして様々な感染症の本を読み漁ってみましたが、読んで数週間経ってしまうとせっかく学んでも忘れてしまっていることが多いのも事実…。
というように、日々の感染症診療に悩んでいた当時初期研修医だった自分に、上級医がすすめてくれたのがこの1冊です。
本書を読むことで今後は尿路感染症のようなコモンな疾患はもちろん、見たこともない菌腫の感染症の患者さんに出会ったとしても自信を持って対応することができます!
また、COVID-19を始めとする年々アップデートされる感染症治療について、遅延なく毎年改訂を繰り返しているのも好きがない一冊であるゆえんですね◎
【基本情報】
タイトル:感染症プラチナマニュアル Ver.8 2024-2025
著者:岡 秀昭
出版社:メディカル・サイエンス・インターナショナル
発行年月日:2023/5/12
【ターゲット層】
医学生から後期研修医
【推定読了期間】
7-8時間程度
【本書の特徴】
●感染症診療に必要かつ不可欠な知識を、ガイドラインに準じてわかりやすくまとめたハンディサイズの一冊
●必要な情報のみに絞ってまとめられている一方、臨床の治療方針に関わる論文についても多数掲載
【本書で学べること】
●感染症診療に当たる上で最も重要な8大原則
●各種抗生剤のスペクトラムや使用上の注意点
●コモンな疾患を始め、まれな感染症までも網羅的にカバーしたそれぞれの治療方針
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
●感染症診療の8大原則についてまず通読!
●目次を参考にさらっと通読して、どこに何が書いてあるかざっくり把握(付箋を貼るのも良いでしょう)
●その後は経験した症例の前後で読み直して復習!
【本書のまとめ】
本書は感染症診療に必要かつ不可欠な知識をまとめたハンディサイズの一冊!
本書は感染症診療に従事する、全ての研修医・医師は携帯しておくべき一冊である!
7.『ねじ子のヒミツ手技 1st Lesson』
気管挿管や末梢静脈路確保、CVC留置といった基本手技を学べる決定版と言えばこの一冊です。本質的な内容であるからこそ、出版から何年立っても色褪せませんね◎
見やすくて面白いイラストと、随所にちりばめられた手技のコツのおかげで、手技に対しての苦手意識を克服することができます。
手技は準備が8割といわれるように、どのような物品が必要でどんな風に準備するかにも言及されている、研修医必読の参考書と言えるでしょう。
将来指導する側になっても役に立つ、必ず一冊は持っておきたい参考書の一つです。
【基本情報】
タイトル:ねじ子のヒミツ手技 1st Lesson
著者:森皆 ねじ子
出版社:出版会社SMS
発行年月日:2009/6/29
【タイプ】
図表多め・手技項目別
【ターゲット】
看護学生~看護師
医学生・初期研修医
【推定読了時間】
3-4時間
【背景・作者の想い】
手技ごとにコツや注意点を図解しており、手技を行う前後で読むことを想定している
※通読せず、効率的に飛ばし読みすることを推奨
自分なりのポイントやルールを書き加えていき、「あなたのヒミツ手技」を作っていく
【学べること】
●手技を行う前の効率的で過不足のない物品準備
※自分で準備できなければスタートラインにも立てません!
※自分で点滴を組み立てることはできますか?
※CVの際に注意すること、患者さんの体位や自身のポジショニングのポイントは?
●外来や病棟で必要となる様々な基本的手技のポイントや注意点
◎採血・注射 ◎気道確保・挿管 ◎CV・Aライン ◎各種ドレーン ◎硬膜外麻酔 その他多数
●自分自身が指導する側に立った際の後輩への的確なアドバイスに必要な知識
※初めてAラインにトライする後輩に伝えるべきポイントや注意事項は?
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
※Amazon評価:
8.『竜馬先生の血液ガス白熱講義150分』
●血液ガスをいつとるべきかわからない…
●ガスの所見をなんとなく眺めているけどいいのかな…
そんな風に曖昧に血液ガス分析の結果を使っていては非常にもったいないです!
血液ガス分析の結果だけでも、患者さんの病態が予測できることもあるのです。
一方で、初学者にとっては覚えるべき数字や式も多く、ハードルが高く感じるのもまた事実です。
そんな複雑な血液ガス分析をたった2時間半で楽しくわかりやすく教えてくれるこちらの一冊です。
夜ご飯を1回外食にするくらいの値段と時間で血液ガス分析を一通りマスターできてしまいます。
そのような観点からも、血液ガス分析を学びたい研修医にとっては最強の一冊と言えるでしょう!
【基本情報】
タイトル:竜馬先生の血液ガス白熱講義150分
著者:田中 竜馬
出版社:中外医学者
発行年月日:2017/2/8
発行年月日:2014/2/25
【タイプ】
講義型
【ターゲット層】
初期研修医1年目(特に前半)
【推定読了期間】
2-3時間程度
【本書で学べること】
●血液ガス所見を読む際に必要な用語、概念
例)PAO2の「A」って何でしょう?
A-aDO2の計算式の意味を理解せず、丸暗記していませんか?
●血液ガスから真の低酸素血症の原因を見つけ出す評価方法
※低酸素血症≠呼吸器疾患!
●pH正常の血液ガス所見に隠された代謝異常を見つけ出す方法
例)ΔAG・補正HCO3-を計算してますか?
●複雑な病態を明らかにする補正式の計算方法と適切な代償の判断
例)このガス所見は代謝性アシドーシスを呼吸性に代償…出来ているのかいないのか?
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
※Amazon評価:
【本書のまとめ】
本書は血液ガス分析を学ぶ初学書として必ず一読すべき一冊である!
9.『疾患と異常像がわかる! エコーの撮り方 完全マスター 』
●心臓エコーはいつ当てても肺がかぶってうまく見えたためしがない…
個人的にも、初期研修医時代に最も苦手意識を持っていた手技がエコーです。
そもそも、正常な像を描出できない時点で異常所見を認知できるわけがないので、なんとか正常像を出せるよう練習を重ねるのですが…やはり上手くいかないことが多いです。
そんな迷える研修医の強い味方となるのがこの一冊です。
エコープローベの持ち方から、当て方のコツ、そもそも何が見えているのかなど、解剖学の観点から非常にわかりやすく解説されています。
この本を手にもって同期と生理検査室に通って、エコーをマスターしましょう!
タイトル:疾患と異常像がわかる! エコーの撮り方 完全マスター
著者:種村 正
出版社:医学書院
発行年月日:2015/5/15
【ターゲット層】
初期研修医から後期研修医
【推定読了期間】
5-6時間程度
【本書で学べること】
●心臓、肝臓など全身臓器の正しいエコー検査方法
●日常診療でよく出会う疾患のエコー所見
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
【本書のまとめ】
本書はエコー検査を学ぶ初学者にとって必須の参考書の一つである!
10.『読み方だけは確実に身につく心電図』
研修医になった瞬間、国家試験ではパターン認識である程度解決できていた心電図の解釈も必要になります。
しかも心電図波形の診断だけではなく、診断を付けた後の追加検査や治療についての知識も必要となります。
かく言う私も学生時代は本当に心電図が苦手で、国家試験でもかなり苦労しました。
臨床に出てからもその苦手意識は残ったままで、誰か一通り心電図を読影する手順をわかりやすく教えてほしい…そんな本はどこかにないのだろうか…と切実に願ったものです。
そして、昨年出版された本書を読んで、まさにこの本こそがそのニーズを満たすと確信しました。
本書を読み進めることで、圧倒的にわかりやすくコンパクトな読影手順を学ぶことできます。そして、その手順は実臨床での実用性も非常に高いです。
初学者が一番知りたい、短時間で見落としなく心電図を読む方法を知ることができるので、ストレスなく心電図の読影をすることができるようになるでしょう。
タイトル:読み方だけは確実に身につく心電図
著者:米山 喜平
出版社:羊土社
発行年月日:2022/11/29
【ターゲット層】
心電図に関わる全ての医療系学生、医療従事者
【推定読了期間】
4~5時間程度
【本書の特徴】
●短時間で見落としなく心電図を読む方法を20ページに凝縮している
●初学者向けの、短時間で心電図を読む方法に徹している
【本書で学べること】
●国家試験勉強で学んでいる心電図の知識を、どのように臨床に生かすのか
●短時間で見落としなく心電図を読む方法
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
※Amazon評価:
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
●まず一章20ページを通読!
●2章で問題演習を繰り返し、読影を身につける!
●3章でさらに詳しい情報を肉付け!
●その後は経験した症例の前後で読み直して復習!
【本書のまとめ】
本書は“短時間で見落としなく心電図を読む方法を知るのにベストな一冊である!”
11.まとめ
いかがだったでしょうか?気になる一冊は見つかりましたでしょうか?
将来どの診療科に進むとしても、ずっと使い続けられる参考書のみをまとめました。
きっとこれらの参考書は今後の研修医生活のどこかで必ず必要となるものばかりなので、迷った際にはこれを機会にまとめて購入するのもいいと思います。
それぞれの書籍の詳しいレビューも書いておりますので、買うかどうか迷っている方はそちらも合わせてチェックしてみてくださいね。
この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は
今後も定期的に記事を更新していきますので
各種SNSの登録よろしくお願いいたします!
【公式ラインアカウント】
各種SNSでのコンテンツ配信を定期的に配信!
この中でしか見られない限定動画配信もしています◎
日々のスキマ時間に気軽に見ることができるので、興味があれば是非登録していただければ幸いです!
コチラのボタンをタップ!👇
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!