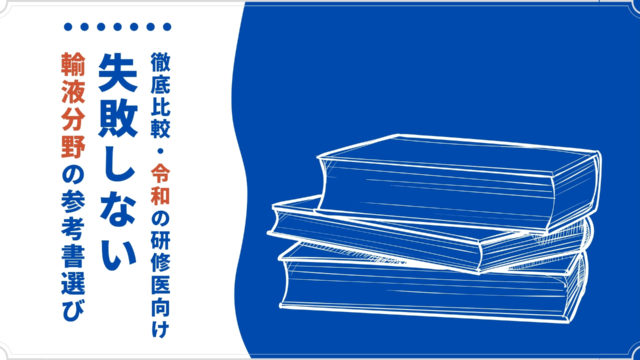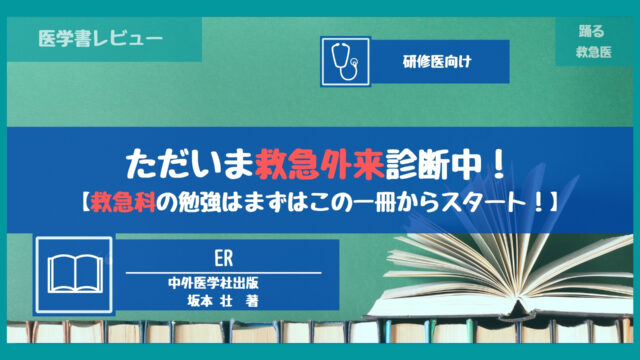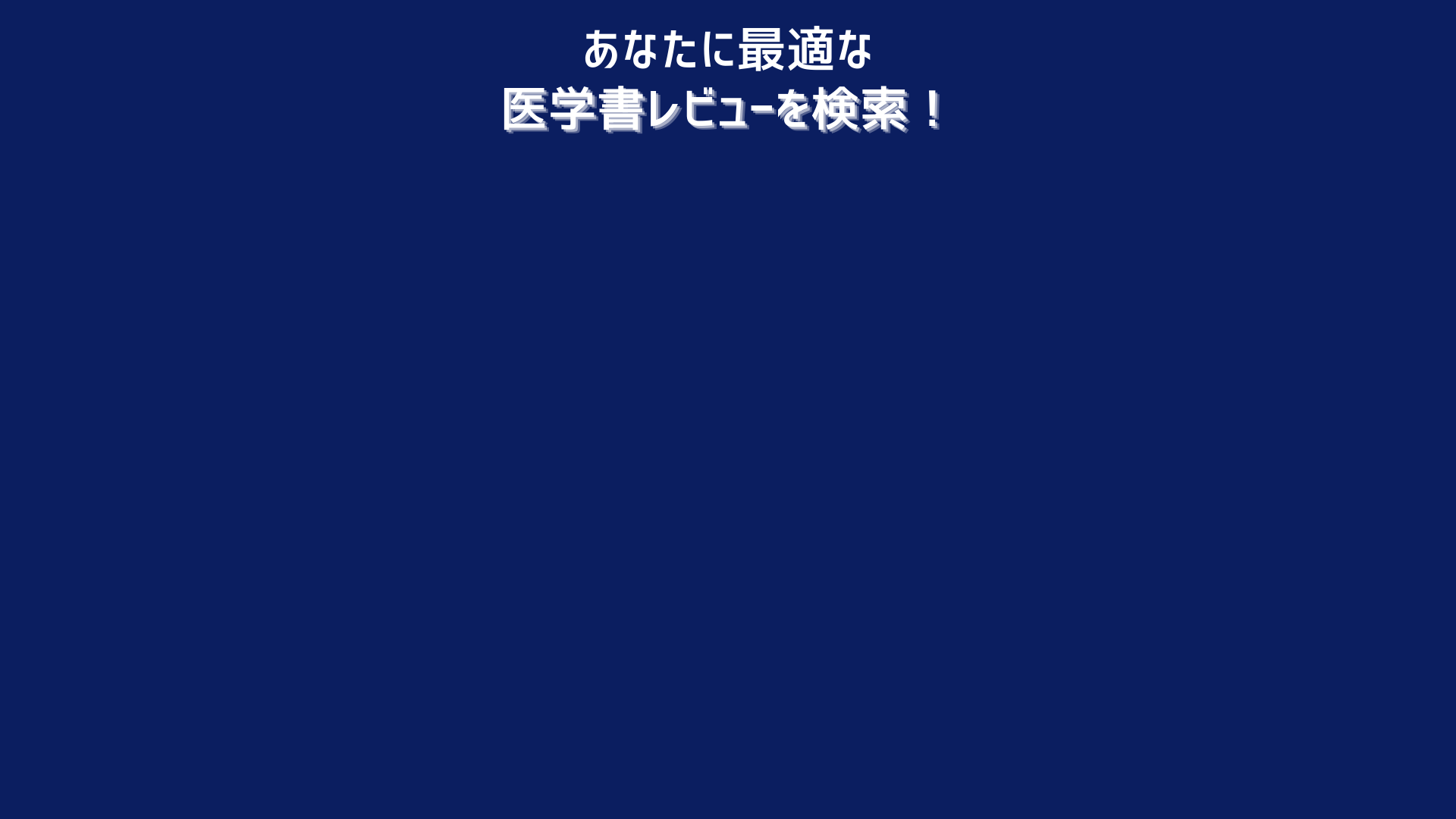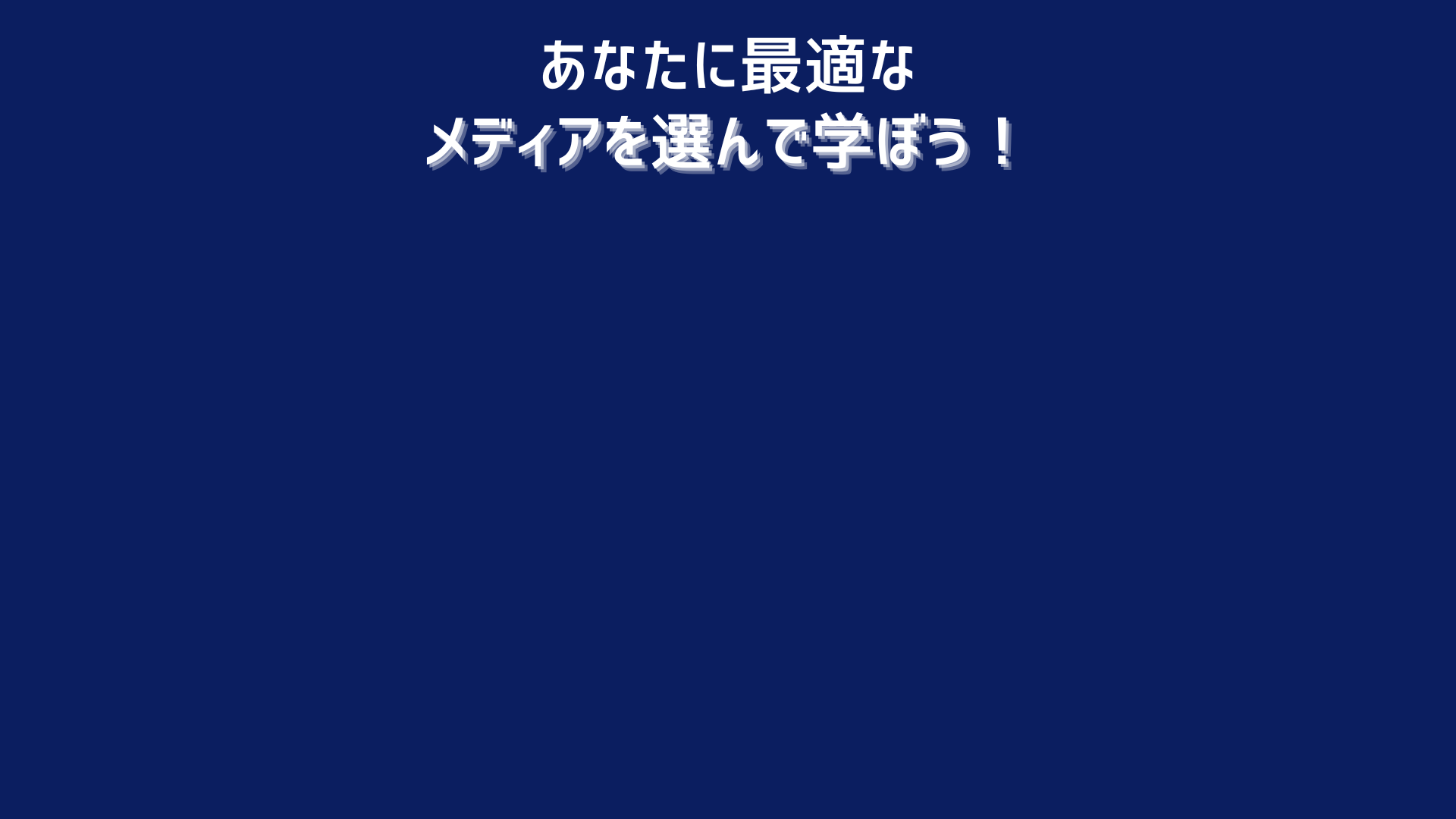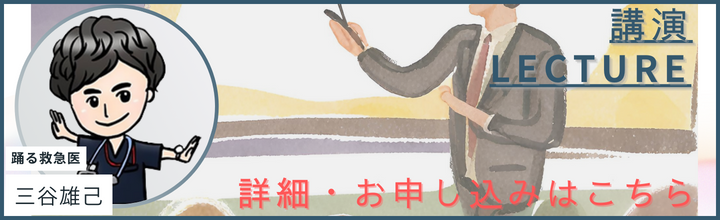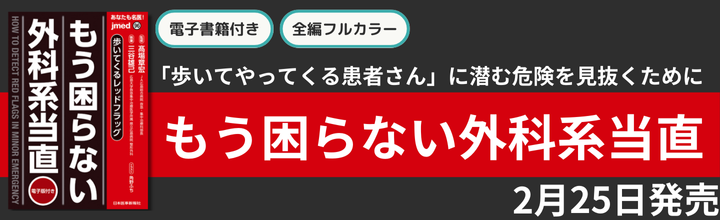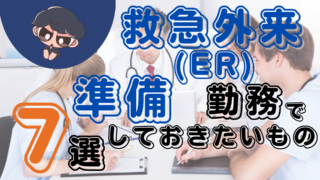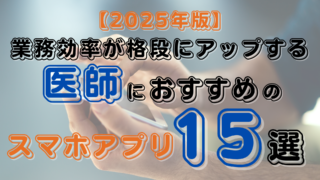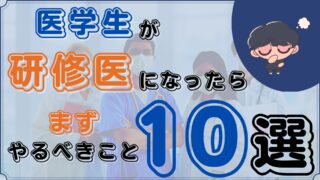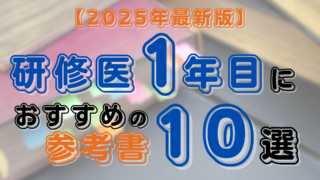「入院患者さんの点滴をオーダーするように言われたけれど、やったことがないから困ったな……。」
「心不全や透析患者さんなど、イレギュラーな症例での点滴ってどうすればいいのかな?」
こういった輸液分野に関する疑問や質問は、日々病棟で後輩と仕事をする中でよく投げかけられる内容ですが、初期研修医の先生方が入職した際には必ず質問されるものでもあります。
私自身も初期研修医の頃、輸液分野はわからないことばかりで困ったのを覚えています。
時を経て、教える立場になったのはいいですが、今度はうまく初期研修医の先生方の疑問を解消できていないと感じることがしばしば出てきました。
そんな時、本書との出会いが輸液について学び直す機会を与えてくれ、輸液を考える際・教える際のコツを知ることができました。
輸液をルネサンス(再定義)すると言う本書は、輸液を初めて学ぶ初期研修医の先生方にはもちろん、知識をまとめ直したいという専攻医以上の先生方にもおすすめです。
本書を読むことで、今後輸液を行う際に自信を持って実施することができます!
輸液について一つでも疑問を持った時に読むべき一冊として、私が是非おすすめしたいのがこちらです。
1.本書のターゲット層と読了時間
【ターゲット層】
・突然担当患者さんの点滴オーダーを任されて困っている初期研修医の先生方
・膨大な輸液分野の知識に振り回されて、結局何を指標に点滴をオーダーしていいのか勉強すればするほどわからなくなっている先生方
・輸液療法を経験則である程度こなすように行っている、専攻医以上で輸液分野の学び直しがしたいと考えている先生方
【推定読了期間】
2-3時間程度
2.本書の特徴
【本書の特徴】
- 輸液療法の考え方を“維持・補正・蘇生”の3つに整理して解説
- 体内分布などの基礎から病態ごとの生理動態まで、エビデンスに基づき症例ごとに解説
が特徴の一冊です。
本書は、ひたちなか総合病院 救急・総合診療科 救急総合内科医長である柴﨑 俊一先生が編集されたものです。
本書を読むことで学べる項目は特徴的なものをピックアップすると、このようになります👇
【本書で学べること】
- 輸液を説明する時に、理解しやすくするために触れるべき事項
- 研修医向けに、病態ごとに合わせた、輸液療法の考え方
- 専攻医向けの、輸液分野における最新のエビデンス・知見
これらは研修医の先生方・専攻医以上の先生方にとって、今後輸液を行う機会があれば必ず役に立つ、学んでおくべき大切な事項であると思います。
3.個人的総評
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
※Amazon評価:
本書の特徴はなんと言っても、輸液療法の考え方を“維持・補正・蘇生”の3つのRに整理して解説しているところです。
その上で、国家試験にも出てくるような体内分布などの基礎から、臨床で考えるべき病態ごとの生理動態まで詳しく解説されています。
また、これら輸液の解説をエビデンスに基づいて行っているのも注目ポイントの一つです。
本書を読むことで、いかに普段、経験に基づいて輸液療法を行っているかを再認識しました。
特に、夜間のルートキープの必要性について、改めて文献の内容を参照しつつ考えた機会は少なかったので、ルートキープについてのコラムはとても新鮮でした。
私自身この本を読んでいて、“輸液負荷の時の流量”について初期研修医の時とても悩んでいたのを思い出しました。
こんな本を初期研修医生活の初めから読めるなんて、本当に羨ましいです!(笑)
また、輸液分野の学習にある程度慣れている専攻医以上の先生方にも、輸液分野における最新のエビデンスが掲載されているので、学びの深い一冊となっています。
中でもの徳竹 雅之先生が執筆されている「蘇生輸液の最近のエビデンスあれこれ」は、我々専攻医も学ぶべきポイントでした!
私も大好きな蘇生輸液の分野ですが、本書ではRevised Starlingやグリコカリックスなどの少し高度な知識を要する内容にも触れられています。
そして学びだけではなく、後輩に教えるという視点から見ても非常に有用な本だと感じました。
私自身、本書でエビデンスを学んだ上で、その知識と経験を交えて後輩に教えることで、格段に早く理解してもらえるようになったと感じており、嬉しい限りです。
ちなみにルネサンス(Renaissance)という単語はよく耳にしますが、実は意味をきちんと理解しないまま使っている単語の代表なのではないでしょうか。
調べてみると、「再生」(re-:再び + naissance:誕生)を意味するフランス語、なのだそうです。輸液という医学において古くからある固定概念を、今の医学に適応できるよう改めてシンプルに再定義して学び直す「輸液ルネサンス」は素敵なテーマだと感じました。
その他の使い方としてはICUやERなど、蘇生分野の輸液療法の入門書としても非常におすすめです。
4.おすすめの使い方・読み進め方
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
- 輸液分野については、まずはざっと通読!
- よくある症例を、詳しく確認
- その後は経験した症例の前後で読み直して復習!
個人的におすすめの使い方をご紹介します。
著者個人の意見としては、まずはざっと輸液分野について通読してしまうことがおすすめです。
本書の輸液療法の項は1-2時間くらいで通読できてしまうので、時間のある時にざっと読み進めるのが良いでしょう。
その後は、心不全や低K血症など、本書に登場するような症例に出会う度に参照しながら業務にあたるとより理解が深まります。
実際の臨床現場では、書籍通りにいくこと、いかないことがそれぞれ出てくると思います。
その際には、本の知識と、実際の現場のギャップを自分なりに理解していくことがより深い学びになるのではないかと思いました。
そのあとは実際の症例を通じてインプットとアウトプットをたくさん経験していきましょう。
何度も復習をすることで、輸液で迷うことが無くなるまで詳しくなっていきましょう!
5.まとめ
【本書のまとめ】
本書は輸液を学ぶ初期研修医にとって必須の参考書の一つである!
本書は、専攻医になっても役立つエビデンスを多く紹介した一冊ある!
まとめると、本書は輸液療法について、体系的に深く学ぶことができる本当におすすめの一冊です。
この一冊を通じて学ぶことで、今後輸液を行う・教えるチャンスが訪れた時に自信を持って取り組むことができます!
今後の学びや業務をより良いものにしたい方には是非手にとっていただきたい一冊です◎
以下に要点や基本事項をまとめましたので、
購入する際には是非参考にしていただければ幸いです👇
【基本情報】
タイトル:レジデントノート 輸液ルネサンス〜維持・補正・蘇生の3Rでシンプルに身につく輸液のキホン&臨床実践
著者:柴﨑俊一/編
出版社:羊土社
発行年月日:2022/04/12
【ターゲット層】
・突然担当患者さんの点滴オーダーを任されて困っている初期研修医の先生方
・膨大な輸液分野の知識に振り回されて、結局何を指標に点滴をオーダーしていいのか勉強すればするほどわからなくなっている先生方
・輸液療法を経験則である程度こなすように行っている、専攻医以上で輸液分野の学び直しがしたいと考えている先生方
【推定読了期間】
2−3時間程度
【本書の特徴】
- 輸液療法の考え方を“維持・補正・蘇生”の3つに整理して解説
- 病態ごとの生理動態まで、エビデンスに基づき症例ごとに解説
【本書で学べること】
- 輸液を説明する時に、理解しやすくするために触れるべき事項
- 研修医向けに、病態ごとに合わせた、輸液療法の考え方
- 専攻医向けの、輸液分野における最新のエビデンス・知見
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
※Amazon評価:
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
- 輸液分野については、まずはざっと通読!
- よくある症例を、詳しく確認
- その後は経験した症例の前後で読み直して復習!
【本書のまとめ】
本書は輸液を学ぶ初期研修医にとって必須の参考書の一つである!
本書は、専攻医になっても役立つエビデンスを多く紹介した一冊ある!
この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は
今後も定期的に記事を更新していきますので
各種SNSの登録よろしくお願いいたします!
【公式ラインアカウント】
各種SNSでのコンテンツ配信を定期的に配信!
この中でしか見られない限定動画配信もしています◎
日々のスキマ時間に気軽に見ることができるので、興味があれば是非登録していただければ幸いです!
コチラのボタンをタップ!👇
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!