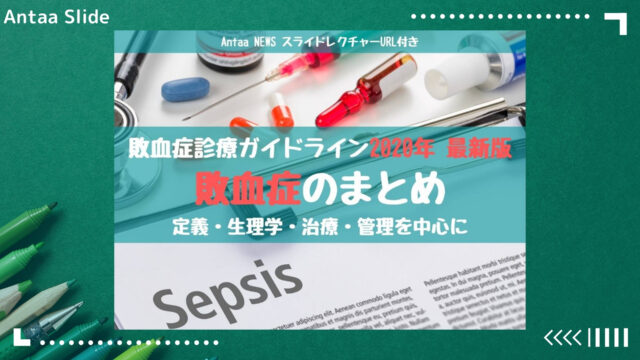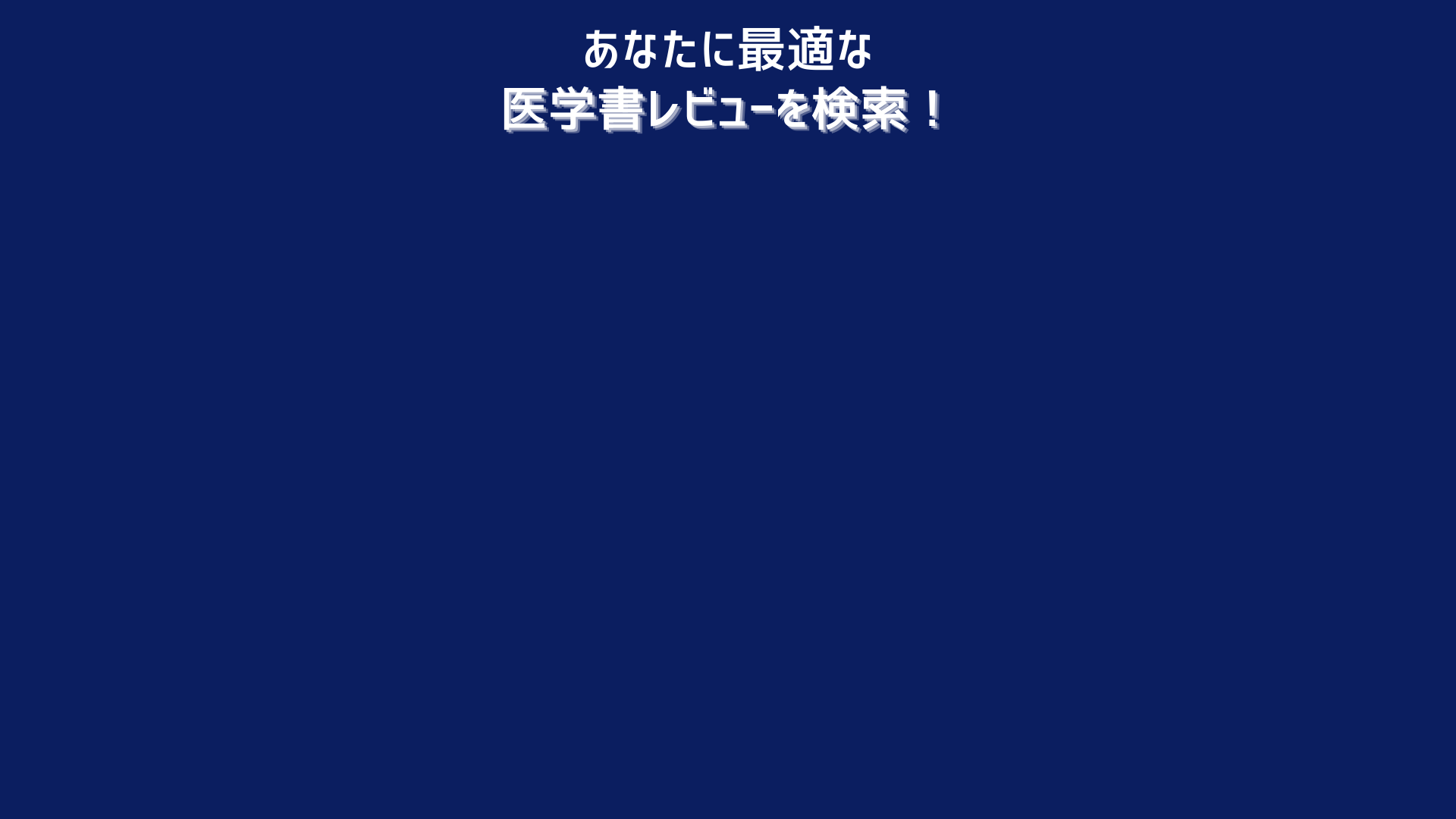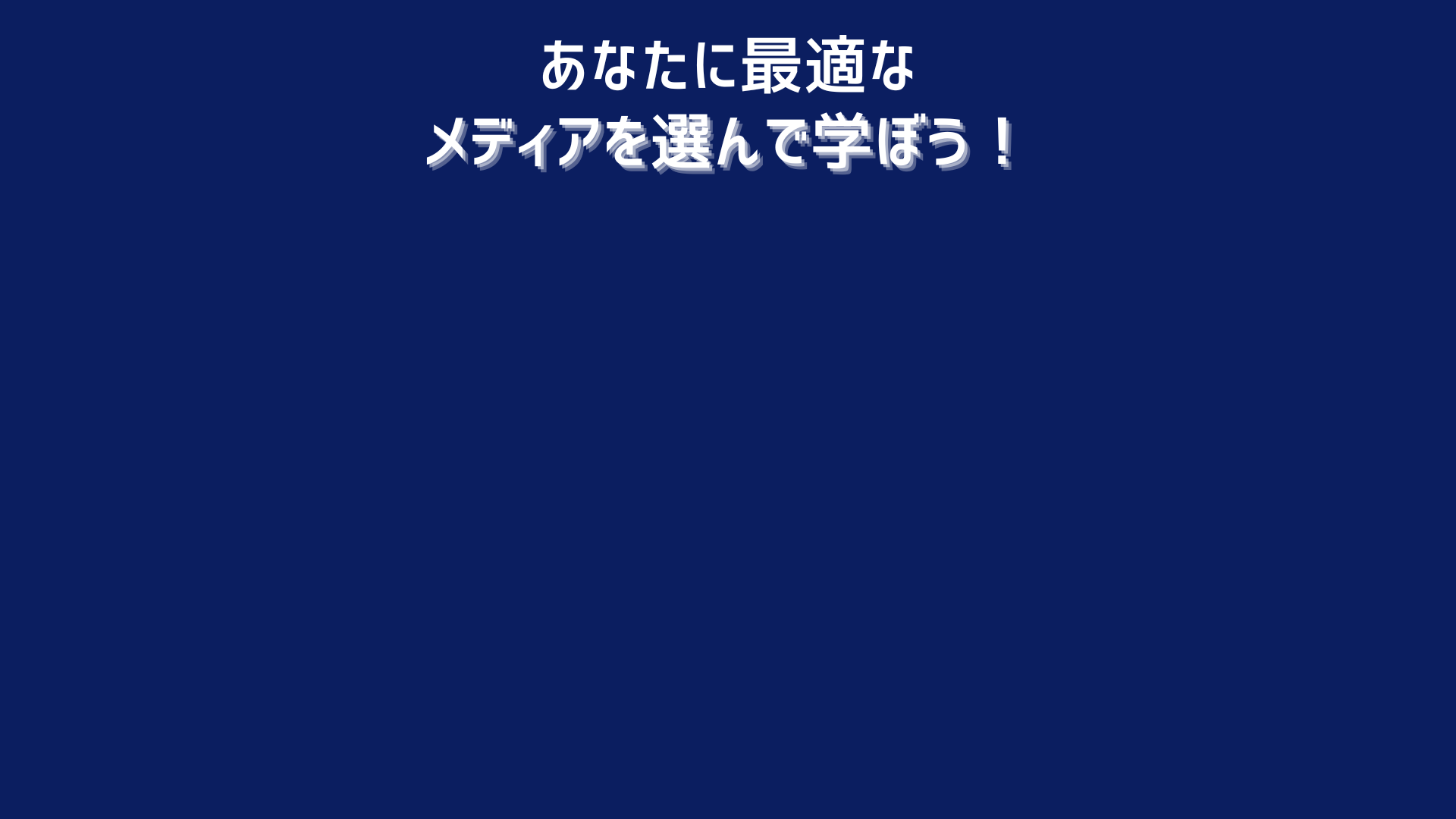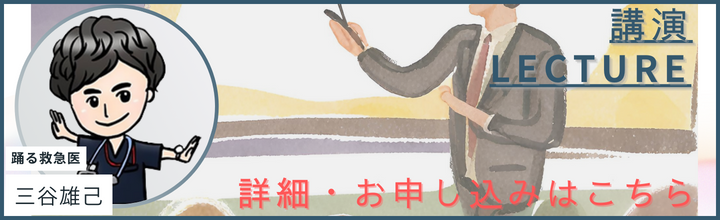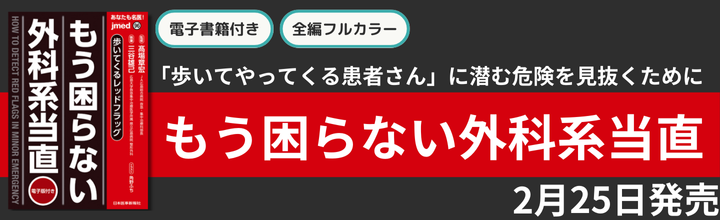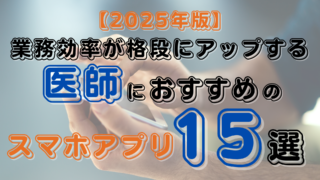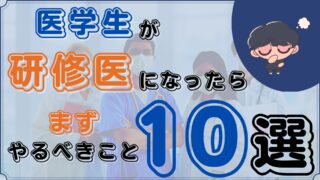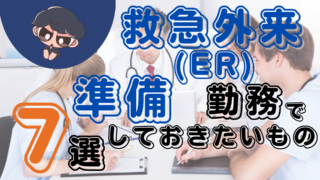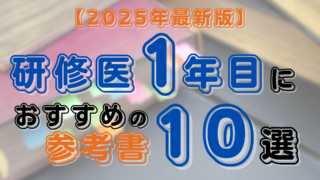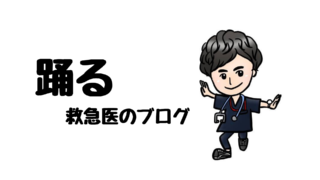
今回は救急・集中治療の分野で遭遇することの多いrefeeding症候群についてまとめました。栄養管理や生化学、生理学の勉強になるので是非通して一読ください。
1.ポイント
●飢餓・低栄養状態の患者に治療開始するときは可能性を考慮
●神経性やせ症、癌、術後、アルコール依存、ホームレスなどは高リスク
●栄養の増量方法は様々だが、リスクに応じてゆっくりとが共通認識
●Pに加え、K、Mgも頻回チェック+補正。ビタミンB1も忘れずに
2.定義・病態生理
低栄養状態にある患者に 急激な栄養投与を行った際、
血管内から細胞内に 体液や電解質が急速に移行し、
低血糖や電解質異常(主に低P血症)により重篤な合併症を来す病態1)
3.疫学
RFSは栄養開始から72時間以内に生じることが多く、それ以降は大きく可能性が下がります2)。
Refeeding Syndromeは患者の死亡率が70%と報告されており、早期発見・予防が重要です。
【リスクファクター】
高リスク群の患者背景として高齢者、担癌患者、神経因性食思不振症が上げられます。
NICE guideline3)では、以下を満たす患者はRFSの高リスクとされています。
【以下の項目 1 つ以上に該当】
●BMI 16 未満
●過去 3 6 か月で 15% 以上の体重減少
●10 日間以上の絶食
●再栄養前の P, K, Mg 低値
【もしくは以下の項目 2 つ以上に該当】
●BMI 18.5 未満
●過去 3 6 か月で 10% 以上の体重減少
●5 日間以上の絶食
●過飲酒歴または以下の薬剤の使用歴
(インスリン, 化学療法 , 制酸薬 ,利尿薬)
ちなみにBMI>18.5であってもリスクなしとは言えないと提言されているので、見た目だけでリスクが低いと判断するのは危険です。
これらのリスク因子を拾い上げるために、以下のような項目に注意しつつ病歴聴取を行いましょう👇
・食事はどのくらいの量が摂れていたか
・入院前と入院後の食事状況
・食事摂取不良の期間
・精神科へ入院中の摂取エネルギー
・記銘力低下・意識変容・作話
・利尿剤の乱用
・下剤の乱用
・精神科の処方の詳細
・サプリメントや漢方の内服がないか
・overdoseの既往
4.症状
【まず想起すべき症状】
●低P血症Hypophosphatemia
●低K血症Hypokalemia
● 低Ca血症Hypocalcaemia
● 低Mg血症Hypomagnesaemia
●ビタミン欠乏(特にチアミン)
●うっ血性心不全
●末梢性浮腫
【臓器別】3)
中枢神経系 Wernicke脳症、Korsakoff症候群、知覚異常
心血管系 不整脈、うっ血性心不全 高血圧、低血圧
呼吸器系 呼吸不全、肺うっ血
腎臓系 浸透圧利尿
筋骨格系 骨軟化症
血液系 白血球・血小板機能不全、溶血、2,3-DPG欠乏
代表的な症状や電解質異常を知っておくことで、もしかしたらrefeeding症候群かも…と早期に認知することが非常に大切です。
リスクが高いと判断している患者さんであればなおさらで、たとえ少量栄養投与を行っていても上記のような症状が出現していれば栄養計画を再検討しましょう。
5.病態・原因
病態生理について簡単に勉強しておきましょう。refeeding症候群のベースには長期絶食期間が存在します。
低栄養状態では糖の供給が低下してリンを介していない脂質代謝であり、インスリン分泌は低下しています。
この期間中に何とか低血糖状態を避けようと、その一方でグルカゴンの分泌は促進されます。
グリコーゲンや脂肪、アミノ酸に加えて電解質やビタミンも徐々に枯渇してしまい、体内のエネルギー源はほとんどなくなってしまうのが問題です。
それに加えて、嘔吐や下痢の消化器症状や利尿薬でバランス異常はさらに悪化してしまいます。
この状況でいきなり栄養を投与すると、インスリン分泌が過剰となり、インスリンの作用により糖・電解質が細胞内シフトします。
ATPや2.3-DPG産生にてリンが細胞内に移動して消費される結果、低P血症などの電解質異常をきたすのです。
また、解糖系のVit B1の大量消費も同時に起きてしまい、結果としてそれぞれの欠乏症状より致死的合併症に至るというのがメカニズムです。
5)引用
低P血症はATP、DNA、RNA、タンパク合成に影響を及ぼし、白血球の走化性や貪食能、血小板凝集能が低下します👇
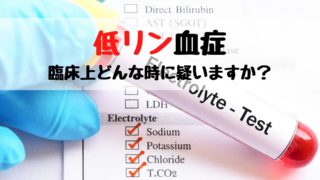
6.検査
【血液検査】
血清P値のフォローは重要です。しかし、体内のPのうち細胞外に存在するのはわずかであり(0.1%)、ほとんどは有機リンとして体内に蓄えられていることに注意します。
血液検査で測定されるのは主に血中の無機リンであり、必ずしも体内のP不足が血液検査値だけでは評価しきれないのです。
【心電図】
低P血症に伴う不整脈に注意しましょう。VTのリスクが高まります。
7.治療
高リスクと判断した患者さんへの栄養療法の進め方は、様々なガイドラインで異なる推奨があるので画一的に決定することはできません。
ですが、基本的には少なめで開始するというのは共通認識であるといえるでしょう。
NICE guideline4)では、RFSのリスクが高い患者に対して、最大でも10kcal/kg/日の栄養から投与を始め、4~7日かけて必要量までゆっくりとカロリーを増量していくことを推奨しています。
特に、BMI<14 kg/m2、15日以上食事をしていなかった等の非常にリスクの高い症例では、5kcal/kg/日から開始し、持続的な心電図のモニタリングも必要といわれています。
2020年の様々なガイドラインの推奨を比較した文献6)では、リスクが高いと判断し少なめから開始するなら5kcal/kg/日、Moderate riskでは10-20kcal/kg/日で開始すべきとされています。
増量のペースは、4-10 日間程度で Full まで漸増 or 2-3 日毎に 2-300kcal ずつ増量
など様々な推奨があり、基本的には臨床経験に基づいて判断してくこととなりそうです。
注意点としては、経静脈的点滴の中にもカロリーは含まれている点です。例えば高K決勝に対して50%ブドウ糖液を用いてGI療法を頻回に行っていると、思った以上に栄養不可になってしまう点に注意しましょう。
少なくとも7日間はNa、K、IP、Mg、BUN、Creは毎日チェックし、心不全・不整脈の合併が多いことから心エコー、ECG検査も行いましょう。特にハイリスクの場合は、電解質は12時間おきに確認することが大切です。
前述したrefeedingを疑う所見が見られたら、栄養の増量は一旦待つ必要があります。
栄養開始後に電解質の補正が困難になる、もしくは急激に低下する場合はカロリーを50%減量し、1-2日毎に目標の約33%ずつ増量するのが妥当な判断とされています。
致死的なレベルの異常であれば栄養中止も検討しましょう。
またRapid turnover protein (プレアルブミン、Retinol binding potein)は再栄養に起因する低リン血症のリスク評価として有効とされていますので、参考にしつつ電解質補正を継続しましょう。
8.引用文献
1) Hisham M Mehanna, et al. BMJ 2008; 336: 1495-98.
2) Natalie Friedli, et al. Nutrition. 2018; 47:13-20.
3) NICE clinical guideline 32, 2006.(Last updated: 04 August 2017)
4)Ornstein RM, et al.J Adolesc Health. 2003;32(1):83.
5)中屋ら:四国医誌 68巻1,2号 23-8 ,2012
6)da Silva JSV et al. Nutr Clin Pract . 2020 35(2):178-195.
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!