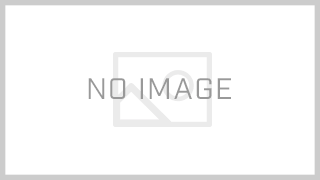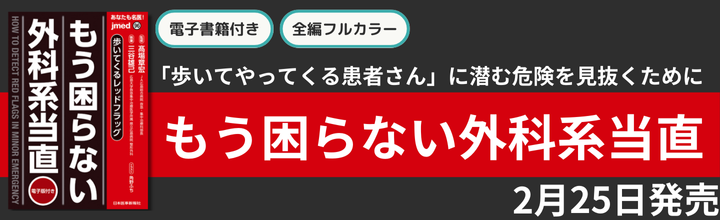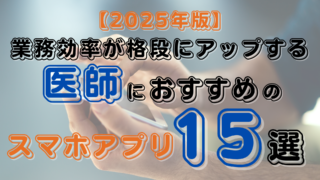セミナー後に届いた、とても重要な質問
先日の敗血症セミナーの後、ICU看護師さんから、こんな質問が届きました。
📩 看護師さんからの質問
「普段はICUで看護師をしており、敗血症・敗血症性ショックの患者さんを受け持つことも多いです。
基本的に37.5℃もしくは38℃以上の患者さんに対して、アイスノンなどでクーリングで対応しています。
薬剤(アセリオ、カロナールなど)による解熱は頻呼吸などの酸素需要の増大、患者本人の苦痛がなければ無理に投与する必要はないと以前医師から言われました。
看護師として解熱薬は熱が上がっている途中で検討したら良いのか、もしくは上がりきった時点で検討したら良いのか、教えていただきたいです。」
とても本質的な質問だと思ったんです。
発熱への対応は、ICUや病棟で毎日向き合う問題ですよね。でも、「なぜそうするのか」「どのタイミングで介入すべきか」を理解している医療者は、実は多くないんです。
この記事では、発熱患者へのクーリングの是非と、解熱薬の使用タイミングについて、最新のエビデンスをもとに説明していきます。
結論から:クーリングは基本的に推奨されない
まず、最も大切なことをお伝えします。
アイスノンなどによる体表冷却(クーリング)は、基本的に推奨されません。
私の所属している広島大学救急集中治療医学でも、クーリングは基本禁忌とされています。
「え、でも現場では当たり前にやっているけど…」と思われた方もいるかもしれません。
なぜクーリングが推奨されないのか、その理由を説明していきますね。
クーリングの何が問題なのか?〜震えと酸素消費量の増加〜
体表を冷やすと、体は「体温が下がりすぎている」と判断します。
その結果、震え(シバリング)が起こります。
🥶 震えが引き起こす問題
震えは、体温を上げるための生理的反応です。でも、これが重症患者さんにとっては大きな負担になるんです。
⚠️ 震えによる悪影響
- 酸素消費量が40-100%増加
- 心拍数・血圧の上昇
- 患者さんの不快感・苦痛
- 人工呼吸器との非同調
特に、敗血症性ショックのような重症患者さんでは、酸素消費量が増えることは致命的です。
ただでさえ酸素供給が不十分な状態なのに、震えによって酸素需要がさらに増えてしまう。これは矛盾した対応なんですね。
エビデンスが示すクーリングの無効性
実際、クーリングの効果を検証した研究があります。
2012年にAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine誌に発表された、Schortgen らのランダム化比較試験では、敗血症性ショック患者さんに対する外部冷却の効果が検証されました。
📊 研究結果(Schortgen et al. 2012)
対象:敗血症性ショックで体温≧38.3℃の患者200名
介入:外部冷却(体表冷却)vs 通常管理
結果:
- 死亡率に有意差なし
- 冷却群では震えが有意に多い
- 臓器障害の改善に差なし
つまり、クーリングは効果がないばかりか、震えという有害事象を増やす可能性があるということです。
では、解熱薬はどうか?〜アセトアミノフェンの効果〜
「じゃあ、解熱薬は使った方がいいの?」
これも重要な疑問ですよね。
2015年にNew England Journal of Medicine(NEJM)誌に発表された、Youngらの大規模ランダム化比較試験(HEAT試験)が、この疑問に答えてくれます。
📊 HEAT試験(Young et al. NEJM 2015)
対象:感染症が疑われる重症患者700名
介入:アセトアミノフェン 1g 6時間ごと vs プラセボ
結果:
- 死亡率に有意差なし
- ICU-free daysに差なし
- 臓器障害スコアに差なし
つまり、解熱薬も、予後を改善するわけではないということです。
ただし、解熱薬には震えを引き起こすリスクはありません。この点で、クーリングよりは安全と言えます。
では、いつ解熱を考えるべきか?
ここまでの話をまとめると、こうなります。
💡 解熱介入の考え方
クーリング(体表冷却)
基本的に推奨されない
- 震えを引き起こす
- 酸素消費量が増加
- 患者さんの苦痛
解熱薬(アセトアミノフェンなど)
予後改善効果はないが、以下の場合は検討
- 40℃を超える高体温で臓器障害のリスクがある
- 頻呼吸・頻脈など、発熱による酸素需要増大が顕著
- 患者さんの苦痛が強い
最も大切なこと
発熱の原因を特定し、原因に対する治療を行う
解熱薬のタイミング〜上がっている途中?上がりきってから?〜
質問にあった「熱が上がっている途中で検討したら良いのか、もしくは上がりきった時点で検討したら良いのか」についてです。
これは、体温の高さと上昇速度で判断します。
⏰ 解熱薬投与のタイミング
40℃を超えそうな場合
上がっている途中で介入を検討
高体温(≧40℃)は臓器障害のリスクが高いため、上がりきる前に解熱を検討します。
38-39℃台の場合
「なぜ上がっているのか」を考える方が大事
- 感染症なら、抗菌薬の選択・投与が最優先
- 発熱による症状(頻呼吸、頻脈、苦痛)が強ければ解熱薬を検討
- 症状がなければ、無理に解熱する必要はない
重要な視点
発熱は「結果」であって「原因」ではない
発熱自体を下げることよりも、なぜ発熱しているのかを鑑別し、原因に対する治療を行うことが最優先です。
感染症なら、抗菌薬が最優先
発熱の原因が感染症であれば、適切な抗菌薬の選択と投与が最も重要です。
Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021でも、敗血症が疑われる場合は1時間以内の抗菌薬投与が強く推奨されています。
解熱薬で体温を下げることに時間を使うよりも、感染源の特定、培養検体の採取、抗菌薬の投与に集中すべきなんですね。
💡 看護師として意識すべきこと
発熱に気づいたら:
- バイタルサインの変化を確認(頻呼吸、頻脈、血圧低下など)
- 感染徴候を探す(咳、痰、尿混濁、創部発赤など)
- 医師に報告し、培養検体採取と抗菌薬投与の指示を仰ぐ
- 解熱薬は、患者さんの苦痛や酸素需要増大が顕著な場合に検討
この順番が大切です。
唯一の例外〜超高体温の場合〜
ただし、40℃を超える超高体温の場合は、話が変わります。
超高体温は、それ自体が臓器障害を引き起こす可能性があるため、積極的な解熱が必要です。
この場合、解熱薬の投与に加えて、場合によっては体表冷却も検討されることがあります(ただし、震えを最小限にするため、鎮静下で行うなどの工夫が必要です)。
🔥 超高体温(≧40℃)の対応
- 解熱薬の投与
- 必要に応じて体表冷却(鎮静下)
- 臓器障害のモニタリング
- 悪性症候群、悪性高熱症、熱中症などの鑑別
まとめ
発熱への対応、整理できたでしょうか。
✨ この記事のポイント
- クーリング(体表冷却)は基本的に推奨されない
- 震えを引き起こす
- 酸素消費量が増加
- 予後改善効果はない
- 解熱薬も予後改善効果はない
- ただし、苦痛や酸素需要増大が顕著なら検討
- クーリングより安全
- 40℃を超える場合は上がっている途中で介入
- 38-39℃台なら「なぜ上がっているのか」を考える方が大事
- 感染症なら抗菌薬が最優先
- 発熱は「結果」であって「原因」ではない
ICU看護師として、患者さんの発熱に気づいたとき、まず考えるべきは「なぜ発熱しているのか」です。
解熱することばかりに目を向けず、原因を特定し、原因に対する治療を行う。
この視点が、患者さんの予後を改善します。
参考文献
- Schortgen F, Clabault K, Katsahian S, et al. Fever control using external cooling in septic shock: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(10):1088-1095.
- Young P, Saxena M, Bellomo R, et al. Acetaminophen for Fever in Critically Ill Patients with Suspected Infection. N Engl J Med. 2015;373(23):2215-2224.
- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Crit Care Med. 2021;49(11):e1063-e1143.
- Drewry AM, Ablordeppey EA, Murray ET, et al. Antipyretic Therapy in Critically Ill Septic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2017;45(5):806-813.