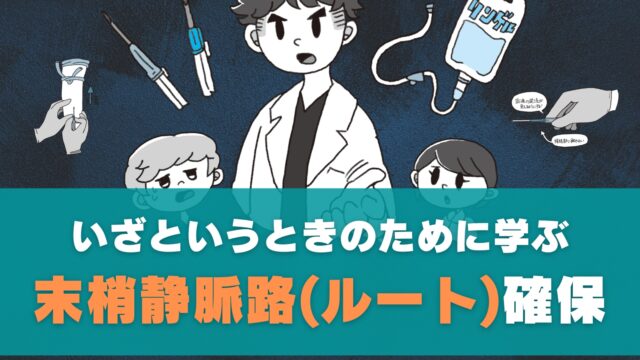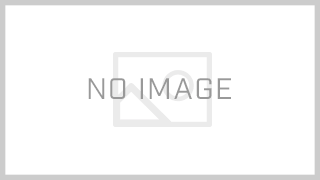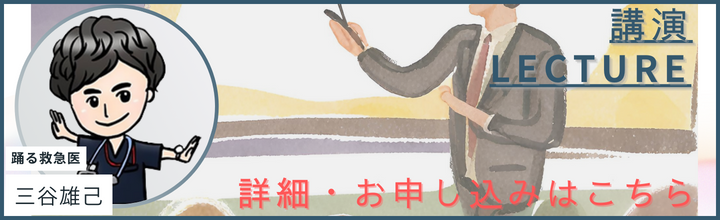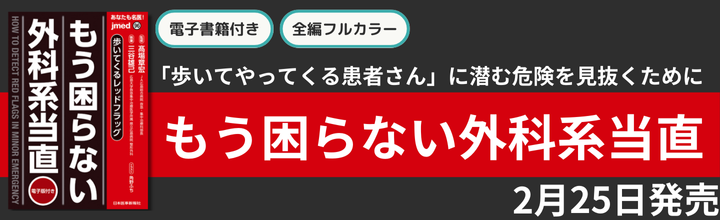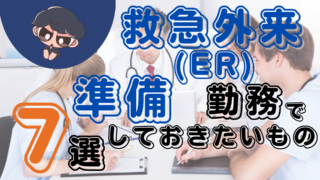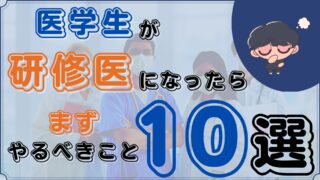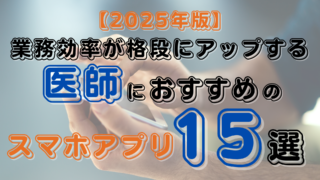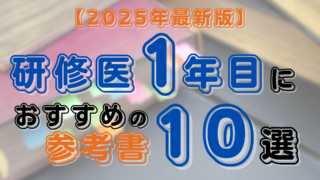【2分でわかる】経鼻エアウェイの使い方
上気道閉塞の患者さんに経鼻エアウェイを挿入する時、適切なサイズを選べていますか?挿入の方向や角度に迷った経験はありませんか?
今回は、気道確保の重要なデバイスである経鼻エアウェイ(Nasal Airway)の使い方について、2分でサクッと整理します。
適切なサイジング、挿入時の注意点、そして安全ピンによる固定の考え方まで。
明日から使える実践的な知識を一緒に学んでいきましょう!
📹 セミナー動画
経鼻エアウェイとは?適応と禁忌
0:00~0:28
経鼻エアウェイは、文字通り鼻腔から挿入するデバイスで、舌根沈下や咽頭などの上気道閉塞を解除するために用います。
経口エアウェイと比較すると、嘔吐反射を誘発しにくいため、使用する場面が多いデバイスの一つです。
適応となる患者さん
舌根沈下や咽頭などの上気道閉塞がある患者さんが適応となります。
禁忌・注意すべき状況
頭蓋骨折を疑う場合は禁忌となります。頭蓋損傷のリスクがあるため、このような患者さんへの挿入は避けましょう。
経鼻エアウェイの適応と禁忌
- 適応: 舌根沈下や咽頭などの上気道閉塞がある患者さん
- 禁忌: 頭蓋骨折を疑う場合(頭蓋損傷のリスク)
- メリット: 経口エアウェイと比べて嘔吐反射を誘発しにくい
- 目的: 上気道閉塞の解除
適切なサイジングの方法
0:28~0:44
経鼻エアウェイもサイジングが非常に重要です。サイズが合っていないと、気道確保が不十分になったり、鼻腔内を損傷してしまうこともあります。
サイジングの基本
経鼻エアウェイには様々な種類があるので、まずは患者さんに合ったサイジングをしていきます。
サイジングの目安は、鼻の穴から耳垂(じすい、耳たぶとも呼ばれます)までの長さです。この長さに合わせてサイジングをしましょう。
サイズ選択のコツ
経鼻エアウェイを患者さんの顔に当ててみて、鼻の穴から耳垂までの長さとちょうど合うものを選びましょう。
経鼻エアウェイのサイジング
- 基準: 鼻の穴から耳垂(耳たぶ)までの長さ
- 確認方法: 患者さんの顔に実際に当ててサイズを確認する
- 重要性: 適切なサイズを選ばないと、気道確保が不十分になったり鼻腔内損傷のリスクがある
挿入手技の実際
0:44~2:11
では、実際の経鼻エアウェイの挿入手技の流れを見ていきましょう。
挿入前の準備
手技を行う際には、エアウェイにしっかりとゼリー(潤滑剤)を塗った上で挿入します。これにより、スムーズな挿入が可能になり、鼻腔内の損傷を防ぐことができます。
挿入の方向
垂直を意識しながら入れていきます。これが経鼻エアウェイ挿入の最重要ポイントです。
鼻腔の解剖を考えると、垂直方向に挿入することで、自然な経路で咽頭まで到達できます。
挿入後の確認
挿入後は、以下の点を確認しましょう。
- 胸郭の上がりを確認する
- 聴診を行い、呼吸音を確認する
- これらの所見から、閉塞が解除されているかどうかを評価しましょう
安全ピンによる固定(オプション)
エアウェイの先端は広がっているので、基本的には奥に深入りするリスクは少ないのですが、そのまま入ってしまうのを防止するために、安全ピンを用いて固定することもあります。
ただし、安全ピンによる固定は特に必須ではありません。もし患者さんの鼻などに刺さってしまいそうだったり、危険がある場合は避けてもらっても大丈夫です。
経鼻エアウェイの挿入手技
- 準備: エアウェイにゼリー(潤滑剤)をしっかり塗る
- 挿入方向: 垂直を意識して挿入する(最重要ポイント)
- 挿入後の確認: 胸郭の上がりと聴診で気道開通を評価する
- 固定: 安全ピンによる固定はオプション(リスクがある場合は避ける)
- 深入りのリスク: 先端が広がっているため、基本的にリスクは少ない
まとめ
0:00~2:11
今回の動画では、経鼻エアウェイの使い方について解説しました。
重要なポイントを振り返りましょう。
- 経鼻エアウェイは上気道閉塞の解除に用いるデバイスで、経口エアウェイと比べて嘔吐反射を起こしにくい
- 頭蓋骨折を疑う場合は禁忌(頭蓋損傷のリスクがあるため)
- サイジングは鼻の穴から耳垂までの長さを基準に行う
- 挿入前にエアウェイにゼリーをしっかり塗る
- 挿入時は垂直を意識する(最重要ポイント)
- 挿入後は胸郭の上がりと聴診で気道開通を確認する
- 安全ピンによる固定はオプション(リスクがある場合は避ける)
経鼻エアウェイは、経口エアウェイと比較して嘔吐反射も起きにくいので、使用する用途も多いデバイスの一つです。
救急現場で適切な気道確保を行うために、これらのポイントを日々の診療に活かしていきましょう!
【公式LINEアカウント Qラボで学ぼう✏️】
救急の基礎をもう少し深く学びたい方へ。
Qラボでは、この動画のような月3回の救急レクチャー動画と、月1回の1時間半リアルタイムセミナー、そして毎週配信の限定記事をお届けしています。セミナーで使用したスライドも配布しており、日々の臨床にすぐ使える内容ばかりです。
興味があれば、ぜひ公式LINEの「Qラボ」で一緒に学びませんか?
詳細やスライドの案内は、下のURLからどうぞ▼
https://line.me/R/ti/p/%40339dxpov