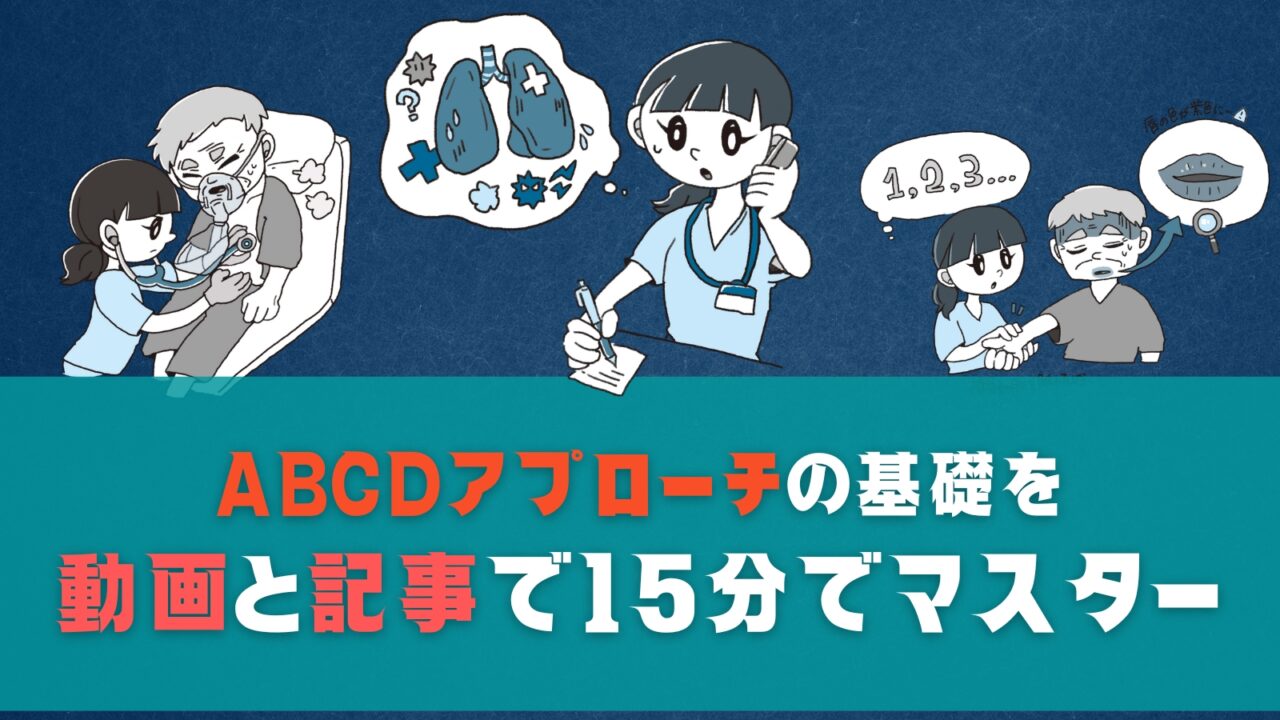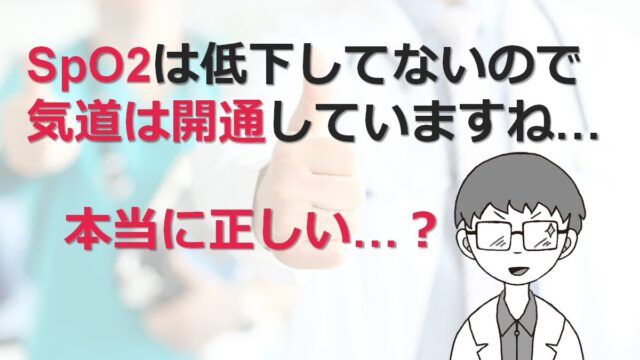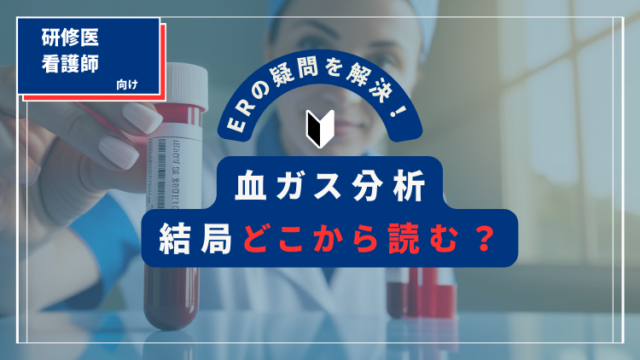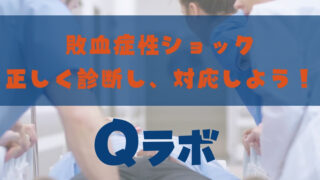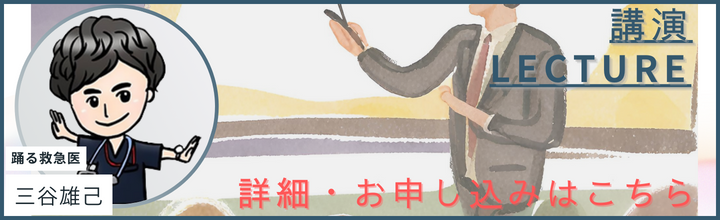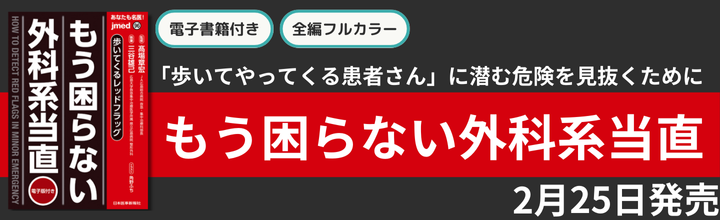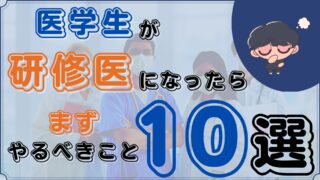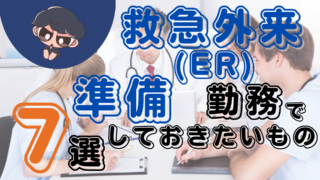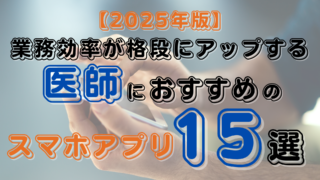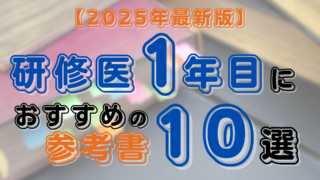救急診療では、「何から手をつけよう」と迷ってしまうこと、ありませんか? 搬送された患者さんを前に、どこで見るのか、何をするのか、誰から対応するのか
意思決定すべきことがたくさんあります。
一方で、ベテランスタッフや上級医は、
「処置室で見ましょう」
「18ゲージで2本確保しましょう」と的確に判断していきます。
この違いは何でしょうか。
今回は、救急診療の総論として、ABCDアプローチの基本的な考え方と、実際の診療の流れを解説します。重症患者さんの初期対応において、酸素の取り込みを念頭に進めるプライマリーサーベイやABCDアプローチをいかに習熟しているかが、明暗を分けます。
救急診療の鉄則を、一緒に整理していきましょう。
📹 セミナー動画
救急診療では迅速な判断が重要
0:00~1:04
救急診療では、迅速な判断が重要とよく言われます。例えば、搬送された患者さんがJCSⅢ-300というかなりの意識障害の状態であったり、収縮期血圧が60 mmHgといったショックを疑うような状態だったりします。
さらに「先生、脈が触れません」となれば、呼吸をしていなければ心肺蘇生を開始しなければならない。
そんな迅速な判断が必要な場面が多いわけです。
そして、意思決定すべきこともたくさんあります。
「この患者さんどこで見ますか?」
「採血や点滴はどうしますか?」
「待合室の患者さんが怒っているんですけど…」
誰から見るのか、どこで見るのか、何をするのか。初期研修の先生方や、まだ救急経験の浅いスタッフの方々は、「何から手をつけよう」と迷ってしまうかなと思います。
- 救急診療では迅速な判断が求められる
- 意思決定すべきことが多い(誰から見るか、どこで見るか、何をするか)
- 初期研修医やスタッフは「何から手をつけよう」と迷いがち
上級医との違いは何か
1:04~2:10
一方で、上級医やベテランスタッフは、「処置室で見ましょう」「末梢静脈路は18ゲージでリンゲル液を2本確保しましょう」「この患者さんを優先して見ましょう」と的確に判断していきます。
これらの両者の違いは、もちろん臨床現場の判断能力――臨床経験や知識の差、初期診療の手際の良さなどもあると思いますが、私自身が一番大きな要因として思うのは、重症患者さんの初期対応において「酸素の取り込み」を念頭に進めるプライマリーサーベイやABCDアプローチを、どれだけ身体に染み込ませているかというところかなと思っています。
- 上級医は的確に判断できる
- 最大の違いは、プライマリーサーベイ・ABCDアプローチの習熟度
- 酸素の取り込みを念頭に進めることがポイント
プライマリーサーベイとは
2:10~3:15
プライマリーサーベイとは、生命維持に関わる生理学的な異常の早期認知に手がかりを置いた診察方法のことです。具体的には、酸素の取り込みの順番
気道(Airway)
呼吸(Breathing)
循環(Circulation)
中枢神経(Disability)の順番に評価を進めて、そこで異常がないかを早期に認知するのがポイントになります。
このプライマリーサーベイは、外傷初期診療において特に重視される概念なんですが、救急診療においてはどんな症例でも、まずはプライマリーサーベイに沿って評価をして、その患者さんが安定しているかどうかを判断するのが一番最初のアクションプランになります。
救急診療の鉄則とも言えるような概念の一つだと思います。
- プライマリーサーベイ=生命維持に関わる異常の早期認知
- 気道→呼吸→循環→中枢神経の順に評価
- どんな症例でも、まずプライマリーサーベイで安定性を判断
- 救急診療の鉄則
ABCDアプローチとは
3:15~4:18
プライマリーサーベイで異常を認知した後は、迅速な治療介入と、治療介入後の効果判定を繰り返す診療のサイクルを継続することが大事です。それが、プライマリーサーベイに治療介入を含めた一連の診察の流れであるABCDアプローチになります。
このアプローチ方法の名前の由来は、気道・呼吸・循環・中枢神経のA・B・C・Dの順番を取ってABCDアプローチと呼ばれます。
これらに加えて、生理学的に重要な全身観察や体温・環境への配慮などを含めたE(Exposure & Environmental Control)も加えて、ABCDEアプローチと呼ばれることもあります。
これらの要素はすべて、生命維持をする上で非常に大切な要素なので、この評価および介入の順番は、このアルファベットの順――A・B・C・Dの順番に行っていくというのが原則になります。
- ABCDアプローチ=プライマリーサーベイ+治療介入+効果判定
- A(気道)→B(呼吸)→C(循環)→D(中枢神経)の順に介入
- E(Exposure & Environmental Control)も加えてABCDEアプローチ
- 評価・介入はアルファベット順が原則
なぜ酸素の取り込みが重視されるのか
4:18~6:28
ここまで、何度も「酸素の取り込み」という言葉が出てきましたが、なぜこんなに酸素の取り込みが重視されるのかについて、少し深掘りしたいと思います。
人間の体の中には、グルコースと酸素を使ってエネルギーを作り出す好気性代謝が備わっています。具体的には、解糖系によって生成したピルビン酸を材料にして、ミトコンドリア内のTCAサイクルでエネルギーを生成します。
しかし、酸素が不足すると、酸素を必要とする好気性代謝がうまく機能しなくなります。そのため、仕方なく酸素を必要としない嫌気性代謝でエネルギーを生成することになります。
ここがポイントなんですが、嫌気性代謝ではグルコース1つに対してATPが2つしか作れないのに対し、好気性代謝では36個のATPが作れます。(ATPはエネルギー源のようなものだと考えてください)
これだけ差があるわけです。酸素がなければエネルギーを作り出す上で非常に効率が悪いので、全身の各臓器や細胞に必要なだけの十分なエネルギーを生成することができません。
嫌気性代謝の状態が続くと、エネルギー不足によって細胞障害や臓器障害へ進展してしまうことが問題になるわけです。
- 好気性代謝:グルコース1つ→ATP 36個
- 嫌気性代謝:グルコース1つ→ATP 2個
- 酸素がないとエネルギー産生効率が18分の1に
- 嫌気性代謝が続くと細胞障害・臓器障害へ進展
- だから酸素の取り込みが最重要
用語の整理:プライマリーサーベイとABCDアプローチ
6:28~7:33
簡単に用語の整理だけしておきます。何度かこの話が出てくるので、お話ししておくと、
- プライマリーサーベイ=評価
- ABCDアプローチ=評価+治療介入+再評価を加えた診療の流れ
これらを実臨床で厳密に使い分けながら話をするということは、基本的にあまりありません。ただ、今回のレクチャーや私自身の書籍などでは、この言葉がよく出てくるので、この違いは一応知っておくと良いかもしれません。
- プライマリーサーベイ=評価のみ
- ABCDアプローチ=評価+治療介入+再評価
- 実臨床では厳密に使い分けないことが多い
救急診療の流れ:搬入前の確認が重要
7:33~8:36
ここからいよいよ本題ですが、救急外来診療の流れについてお話しさせていただきます。この診療の流れの総論を考える上で、まずポイントとなるのは救急隊からの連絡や打ち合わせの部分です。
意外かなと思うんですけど、プライマリーサーベイは診療の一番最初にするべきものだと言われている一方で、実は患者さんが搬入する前から、救急隊からの事前情報や準備をするというところで、戦いは既に始まっているわけですね。
搬入前の確認事項・すべきことを簡単にまとめてみました
- どんな患者さんが来るのかという情報の共有
- どのようなメンバーで初期診療に当たるのかというメンバー同士の自己紹介
- 搬送される患者さんにおいて、どのようなことが予想されるかというポイントの共有
- チームメンバーがそれぞれどのような役割分担で行うのか
- 初期診療をするにあたってのリソースが十分にあるか(挿管デバイス、胸腔ドレーンなど)
- 提案や心配事があるかどうか
これらを受け入れまでの短時間でみんなで確認することがとても大切です。みんなで確認した上で的確な準備を整え、患者さんがやってくるのを待ちます。
- 患者搬入前から戦いは始まっている
- 情報共有、メンバー確認、役割分担、リソース確認が重要
- 受け入れまでの短時間でチームで確認する
第一印象の評価:15秒で重症度を見抜く
8:36~10:47
患者さんが救急外来に搬送されたタイミングで行うべきなのが第一印象の評価です。これは、救急車内から処置室・診察室まで搬送される間の数秒間~1分間ぐらいの間に評価をするのがポイントになります。
具体的には15秒程度でやりましょうと言われたりしますが、パッと見のジェネラルアピアランス(顔色や患者さんの外観)を見て、この患者さんが重症かどうかを評価し、その次にABCDEの項目をそれぞれ簡潔に評価していきます。
実際の評価する流れを説明すると
- 患者さんに呼びかけながら、橈骨動脈の脈の触れを確認する
- スムーズに自分の名前を言うことができれば、ある程度気道と意識が保たれていると評価できる
- 脈の触れや末梢冷感を感じながら、呼吸様式を同時に確認していく
- 浅くて早い呼吸、しんどそうな努力呼吸があれば、呼吸に異常があるかもしれない
- 末梢冷感や脈の触れが弱ければ、C(循環)に異常がある可能性がある
- 手を触れつつ、明らかな異常体温や、低体温をきたすような衣類の濡れがないかなど、Eについても合わせて評価する
これらの第一印象の評価をする流れを何度も繰り返して慣れてくれば、15秒程度で「どの項目にどの程度の異常がありそうか」を大まかに認知できるようになります。
- 第一印象の評価は15秒程度で行う
- ジェネラルアピアランス+ABCDEを素早く評価
- 呼びかけ、脈触知、呼吸様式、末梢冷感、体温を同時に確認
- 何度も繰り返して慣れることが大切
重症度の早期認知が最も大切
10:47~11:50
この重症度・緊急度の早期認知は、救急診療において非常に大切です。第一印象の評価ではこれを一番のポイントにしています。緊急度・重症度を早期に認知することで、
- どこで対応すべきか
- 今診療に当たろうとしているメンバーで十分なのか
- 機材の準備が間に合っているか
といったことを、早い段階で判断することができます。
そして、重症度を評価した後に、もう一つ大切なことがあります。私が好きな本の一節から紹介させていただきます。
『THE BOY, THE MOLE, THE FOX AND THE HORSE』(邦訳タイトル『ぼく モグラ キツネ 馬』)という本の中で、男の子が馬に尋ねるわけですね。「あなたが今まで言った中で一番勇敢な言葉は何?」と聞いた時に、馬は答えました。「助けて」という言葉です。
これはまさに救急診療だなと思ったので、ここで引用させてもらいました。いざ助けを呼ぼうとすると、自分の評価が間違っているんじゃないかとか、自分だけでは対応できないんじゃないかと思われるのが恥ずかしいとか、そういったネガティブな感情がつい働いてしまいます。
ですが、そういった不安を抱えたまま一人で重症患者の診療に当たるのは非常に危険です。目の前の患者さんの重症度が少しでも高そうだと判断したら、躊躇なく助けを呼ぶことが大切かなと思います。
- 重症度・緊急度の早期認知が最優先
- 一番勇敢な言葉は「助けて」
- 助けを呼ぶことは決して恥ずかしいことではない
- 躊躇なく助けを呼ぶことが患者さんを救う
OMI:まず最初にすべきこと
11:50~12:53
そもそも助けを呼ぶことは決して恥ずかしいことではありませんし、重症患者さんへの治療介入は、多くの場合一人で完結するのは難しいのも事実です。どれだけ慣れていたり自信があったとしても、すぐに助けを求めるべきだと思います。
助けを呼ぶのは勇気のある行動であって、チームで患者さんを救う救急診療においては欠かすことのできないアクションかなと思います。
そして、助けを呼びながらできることもいくつかあります。それがOMIと呼ばれる、いろんな教科書でも言われているポイントです:
- O:酸素投与(Oxygen)
- M:モニター装着(Monitor)
- I:末梢静脈路確保(IV line)
これらは、救急外来に搬送される場合であれば、ある程度自動的にモニターをつけたり酸素をつけたり、点滴を取ろうと思えたりするんですけど、院内急変などの場面ではモニターがついていないことがあったり、酸素配管が近くにないということがあったりします。そういったものがあるところに移動するか、もしくはそういったものを持ってくるか、といった介入を考えていかないといけません。
なので、重症患者さんでまず最初にすべきことはある程度決まっています。このあたりはしっかり覚えていただいて、反射的に動けるようにしておくと良いかなと思います。
- 助けを呼びながらOMIを実施
- O:酸素投与、M:モニター装着、I:末梢静脈路確保
- 重症患者さんでまず最初にすべきことはほぼ決まっている
- 反射的に動けるようにしておく
プライマリーサーベイ・ABCDアプローチへ
12:53~14:01
そこから、実際にプライマリーサーベイやABCDアプローチに入っていくという流れになります。
このABCDアプローチやプライマリーサーベイの各論について話そうと思うと、このミニレクチャーの時間では収まりきらないぐらいの内容になってしまうので、こちらについてはぜひ書籍やSNSなども参考にしていただけたら嬉しいなと思います。
まとめ
14:01~終了
今日のセミナーでは、ABCDアプローチ・救急診療の総論について解説しました。
重要なポイントを振り返りましょう。
- 第一印象を評価して重症だと判断したら、助けを呼びながらOMIを実施する
- プライマリーサーベイは、バイタルサインや検査値に囚われず、身体所見で見抜く
- ABCDのA・B・Cの順番から介入と安定化を進めていく
- ABCの安定を確認したら、次の治療方針や必要な検査を考えていく
- 「酸素の取り込み」を常に念頭に置くことが、救急診療の鉄則
- 一番勇敢な言葉は「助けて」。躊躇なく助けを呼ぶ
救急診療の総論を理解することで、迅速な判断と適切な初期対応ができるようになります。ここで整理したポイントを、日々の診療の中で少しずつ実践していきましょう。
【公式LINEアカウント Qラボで学ぼう✏️】
救急の基礎をもう少し深く学びたい方へ。
Qラボでは、この動画のような月3回の救急レクチャー動画と、月1回の1時間半リアルタイムセミナー、そして毎週配信の限定記事をお届けしています。セミナーで使用したスライドも配布しており、日々の臨床にすぐ使える内容ばかりです。
興味があれば、ぜひ公式LINEの「Qラボ」で一緒に学びませんか?
詳細やスライドの案内は、下のURLからどうぞ▼
https://line.me/R/ti/p/%40339dxpov