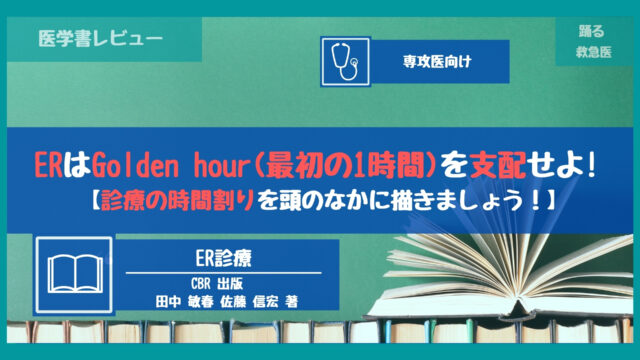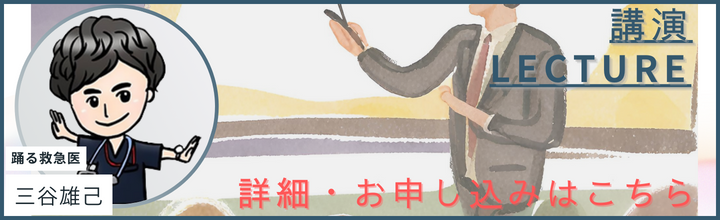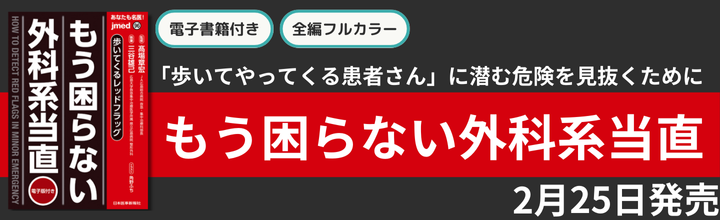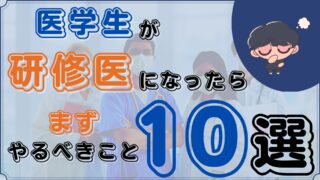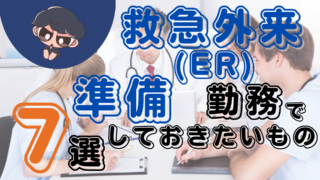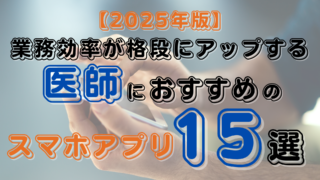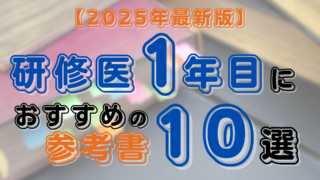専門治療のタイミングや補助循環の導入をどう判断すればいいのか…
急性心不全は救急外来から病棟、ICUに至るまで医療現場で頻繁に遭遇する緊急疾患です。
しかし、その病態は多様であり、適切な循環管理や治療方針の判断は決して簡単ではありません。
「初期対応から専門的治療まで体系的に学べる本が欲しい…」
私自身、ちょうど急性期の循環管理についてより深く学びたいと思っていたタイミングで、ありがたいことに出版社や著者の方のご厚意で本書をご贈呈いただきました。
本書を読むことで、理論だけでなく、実際の症例を通じたリアルな思考プロセスを身につけられ、「こういう場面ならこうする!」と自信を持って判断できるスキルが大幅にアップしました。
今回は、急性心不全診療に携わるすべての方におすすめの一冊として、本書をご紹介します👇
研修医時代から循環器を含め100冊以上の医学書を読み
その中でもオススメの医学書のレビューを月5冊以上書いている
ある救急科専門医のレビューです。
医学生や研修医、各分野の初学者の気持ちが痛いほどわかるので、
是非この一冊を手に取ってみたいと思っていただけるようなレビューを心がけています!
1.本書のターゲット層と読了時間
初期研修医や内科系・救急科の専攻医をはじめ、急性心不全を初めて体系的に学びたい若手医師、循環器内科医志望者
【推定読了時間】
6時間程度
B5判サイズで約264ページと、週末を使えば一通り読み進められるちょうど良いボリューム感です。
忙しい研修医でも数日集中すれば十分読み切れる分量だと感じました。
2.本書の特徴
● 豊富なケーススタディ(Case Live)で実臨床を追体験できる
● 循環動態の理論と治療戦略を“平易な文章”で解説
● 図表・写真・イラストが豊富で視覚的にも理解しやすい
本書の大きな魅力は、「ケーススタディ重視で実臨床に直結する」点です。
理論だけでなく、「実際に患者をどう評価し、どう治療に移すのか」を、症例ごとのディスカッション形式で臨場感たっぷりに学べます。
加えて、文章が“ですます調”かつエッセイ風の語り口なので、循環動態のように難解なテーマも読みやすく、「教科書にありがちな堅苦しさ」が薄い点が大きなポイント。
さらに、オールカラーで写真や模式図が多数掲載されており、実際の心エコー画像やモニタリング波形なども分かりやすく紹介されています。文字だけでは把握しづらい病態を直感的に理解できるのは非常に助かります。
3.個人的総評
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
本書は“ガイドラインや教科書では補いきれない実践的知識”を徹底的に補完してくれる一冊だと感じました。
救急外来で急性心不全の患者さんが来たとき、「呼吸困難が強いから利尿剤を優先すべきか、それとも血圧低下が気になるから血管作動薬を先に使うべきか…」といった迷いが日常茶飯事です。
本書の症例検討では、初期対応から集中治療、さらに循環器内科による専門的介入まで、時系列で丁寧に追ってくれます。そのため、「こういう場合はどの時点で何を考え、何を追加するのか?」が明確にイメージできます。
また、右心不全や心原性ショック、補助循環(IABPなど)の導入タイミングに関する解説も実例と絡めて示されており、「なぜ今、この治療が必要なのか」を循環動態の理論から腹落ちできるのが素晴らしい点です。
さらに、読み物としても面白く、「次のページでどう治療方針が変わるのか?」と気になってスイスイ読み進められます。まさに“物語を追うように学べる”医学書だと思いました。
特に集中治療医の視点としては、集中治療科専門医試験の範囲にも含まれるPVループをはじめとした循環動態の評価について、ここまで噛み砕いて、しかも本質的な内容を簡略化することなく解説している書籍はなかなかありません。
「この本を試験前に読んでおきたかった!」と思うほど、専門医試験を控える方にも最適な構成だと感じます!
また本書では、まず循環動態の基礎をしっかり押さえた上で、症例が少しずつレベルアップしていく流れになっており、イメージしづらい病態や疾患に自然と派生していきます。
その展開の仕方がとても読みやすく、
「読みながらレベルアップしている感覚」があるのも魅力でした!
4.おすすめの使い方・読み進め方
● まず基礎編(循環動態の基礎知識)をざっくり復習
● 各症例を読む前に、「自分ならどう治療するか」をあらかじめシミュレーション
● 症例のディスカッション部分で“答え合わせ”しながらギャップを明確化
● 気になったポイントはメモし、臨床現場で振り返る
● 勉強会や後輩指導用の症例教材としても活用
最初に第1章の循環動態をしっかり理解しておくと、第2章のケーススタディでの学習効果が飛躍的に高まります。
各症例を読む際は「この患者ならどうアプローチするだろうか?」を先にイメージし、それから著者の解説を読むと「答え合わせ」ができ、頭に定着しやすくなります。
また、学んだ内容は必ず現場で実践し、似た患者さんに遭遇したときにメモを見返すクセをつけると効果的です。
症例ディスカッション形式なので、仲間と一緒にグループ学習するのもおすすめです。
【さらに踏み込んで学びたい方へ】
本書には急性心不全だけでなく、虚血性心疾患や敗血症に伴う心筋症(敗血症性心筋症)に関する循環動態の考え方、カテコラミンの使い方なども詳しく記載されています。
特に私自身臨床現場で悩むことの多い、劇症型心筋炎に対する機械的循環補助の最適化というトピックが取り上げられており、集中治療医としても普段悩む場面に対して深い理論背景を学べます。
また、重症大動脈弁狭窄症の患者さんが敗血症を合併するケースなど、「こんな複雑な症例に当たったらどう対処すればいいんだろう?」というリアルな疑問にもしっかり応えてくれるのがありがたいところ。
症例ごとのカンファレンス形式で学べるので、循環器内科・救急科・集中治療科など、それぞれの専門家の視点が交差し、非常に学びの多い内容になっているのでオススメです。
5.まとめ
『循環動態攻略A to Z 急性心不全Case Live!』は、急性心不全診療の実践スキルを総合的に高めてくれる“必読の良書”
本書は急性心不全の初期対応から専門的治療まで一貫して解説しつつ、「なぜその治療を行うのか」の理論的背景を丁寧に説明してくれます。
単なる知識の詰め込みではなく、ケーススタディ形式で楽しく学べる点が最大の魅力です。
特に、循環動態を理解した上での治療選択という視点が徹底されているため、日々の診療で感じるリアルな迷いや不安をスッキリ解消してくれるはずです。
編著:朔 啓太 奥村 貴裕
出版社:メジカルビュー社
発行年月日:2025年2月3日
ターゲット層
初期研修医、内科系・救急科専攻医、循環器内科医志望の研修医・医学生、若手~中堅の医療従事者
推定読了時間
6~8時間程度
【本書の特徴】
●ケーススタディ多数で、理論を“実臨床”に直結できる
●エッセイ風で読みやすく、図表・写真が豊富
【本書で学べること】
●急性心不全の時系列に沿った診療プロセス
●強心薬や血管拡張薬などの具体的な使いこなし方
●補助循環(IABP等)の導入時期や判断基準
【評価】
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
【本書のおすすめの読み方・活用方法】
●基礎理論を押さえてからケースを読む
●自分なりの治療プランを先に考えて“答え合わせ”
●メモを活用して、臨床現場で繰り返し参照
●勉強会や後輩指導に利用し、議論を深める
【本書のまとめ】
循環動態を紐解きながら急性心不全診療を実践的に学べる、まさに“臨床の現場力”が鍛えられる一冊
この記事がお役に立てれば幸いです。
急性心不全をしっかり学び、日々の診療に自信を持って臨みたい方は、ぜひ手に取ってみてください◎
みなさまのリアクションが、今後の記事執筆への大きな励みになります!