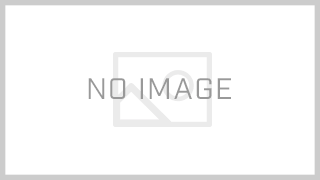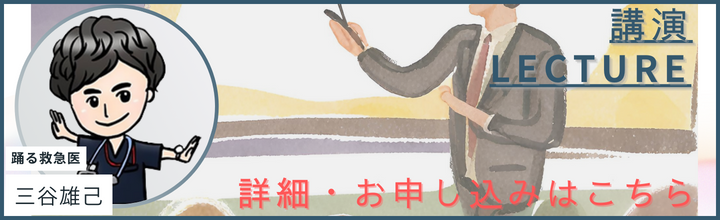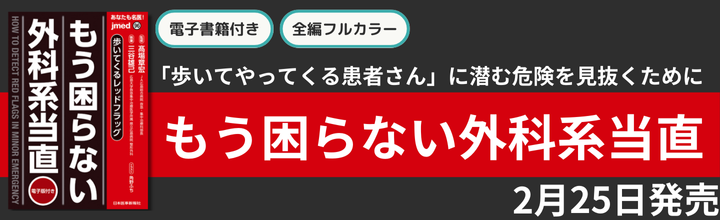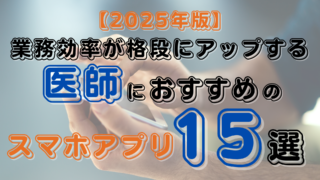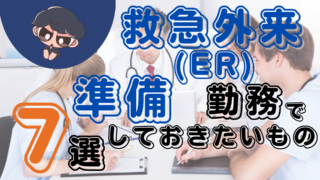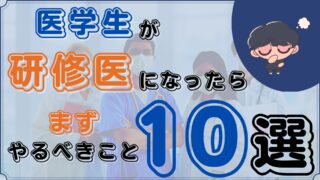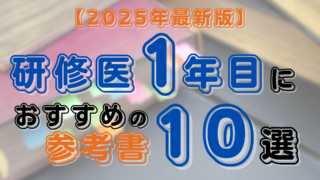エコーを身近にするために:成功体験とモチベーションの話
「心窩部にプローブを当てて、腹部大動脈が見えたら、ちょっと扇のようにあおってみましょう」— 臨床検査技師・井伊さん(エコーセミナー講師)
この一言には、エコーに対する苦手意識を減らし、もっと使ってみたいと思ってもらうための工夫が詰まっています。
Qラボでは、「エコーをどう教えるか」というテーマで、井伊さん・前野先生(救急医)・三谷先生がディスカッションを交わしました。
まずは「出せた」という成功体験を
井伊さんがセミナーで一番大切にしているのは、「まずは出せたという成功体験」です。
「苦手意識を無くして、エコーをもっと使ってみたいと思っていただけるようにしたいと思っています。もし教本どおりにやっても見えないときは、“こうすると見えるかも”というコツを伝えるようにしています」 — 井伊さん
IVC(下大静脈)を描出することは初心者にとって難関ですが、井伊さんはこうアドバイスします。
「心窩部にプローブをあてて腹部大動脈が見えたり、右乳下の肋間で肝臓のヘリが見えたら“儲けもの”。ちょっと扇のようにあおってみましょう」
この「儲けもの」という言葉が象徴的です。完璧を求めず、まずは一歩を踏み出す勇気をくれる指導です。
「まずは出せたという成功体験で、もっとやってみようと思って頂ければ良いなと」 — 井伊さん
「素晴らしいセミナーですね。正直、井伊さんの研修で初期研修を受けたかったです。『まずは出せた』という成功体験、本当に大事だと思います。」 — 三谷先生
ちょっとハードルが高いけれど:LVOT VTIの世界
井伊さんのセミナーでは、さらに高度な内容も扱っています。
「少しハードルが高いかもしれませんが、LVOT VTIを測れるなら、10cm未満ならlow output。一回拍出量(SV)はざっくりVTI×3くらい」
LVOT VTI(左室流出路血流速度時間積分値)とは、心臓のポンプ機能を数値で評価する指標です。ショック患者の評価に役立ちます。
「VMTスコアも左室充満圧を見るのに簡便。IVCと心尖部四腔像を出して、僧帽弁と三尖弁の開くタイミングを見るだけです」 — 井伊さん
「LVOT VTIまで扱えるのはすごいです。集中治療では診療の幅がぐっと広がります。一方、救急では1〜2分での判断が多く、詳細評価は循環器内科に委ねることもあります。 救急としては、“迅速な判断”と“見逃さない視点”の両立を重視しています。」 — 三谷先生
専門や現場が違っても、互いに学び合う姿勢がある。 それがQラボの魅力です。
エコーは「手数」。文化を作ることの大切さ
「当院では年に数回、研修医は必ずエコーセミナーを受けます。当直では毎回一緒にエコーを当てるようにしています」 — 前野先生
エコー教育に熱心な救急医の前野先生は、こう続けます。
「エコーは手数だと思っています。やればやるほど上達する。だからこそ、“エコーを身近にする文化”を作ることが重要です。」
「単発セミナーの価値は、成功体験を通じてモチベーションを作ること。 つい教える側が自分でやって見せたくなるけど、それは自己満足。 “受け手が自分でやってみる”ことこそ大切なんです。」 — 前野先生
「先生のもとで初期研修できる方々は本当に幸せですね。おっしゃる通り、単発セミナーの価値は成功体験とモチベーションを生むことにあります。」 — 三谷先生
「私も継続的でないセミナーでは特に、『戻ってから何をすればいいか』が明確になるように意識しています。“現場で明日から実践できる”、そのきっかけを作ることが一番大事だと思います。」 — 三谷先生
救急と集中治療、それぞれの視点
救急では迅速な判断、集中治療では詳細な評価が求められます。けれど本質は同じ。
「まずエコーを当ててみる」こと。そこから全てが始まります。
今回のディスカッションから学べること
- 「まず出せた」という成功体験がモチベーションを生む
- エコーは手数。日常的に当てる文化を作る
- 教える側の自己満足よりも、学ぶ側の体験を優先
- 現場で明日から使えることを伝える
エコーは、救急や集中治療の現場で欠かせないツールです。苦手意識がある人も、まずは「ひとつのビューでも出せたら成功」です。
困ったときは仲間に相談してみましょう。Qラボには、きっとあなたを助けてくれる誰かがいます。
あなたはエコーにどんな印象を持っていますか? まずは一つ描出してみましょう。その小さな成功体験が、きっとあなたの自信につながります。

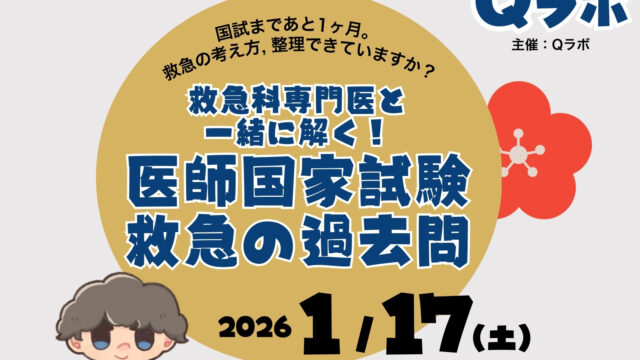
-320x180.jpg)