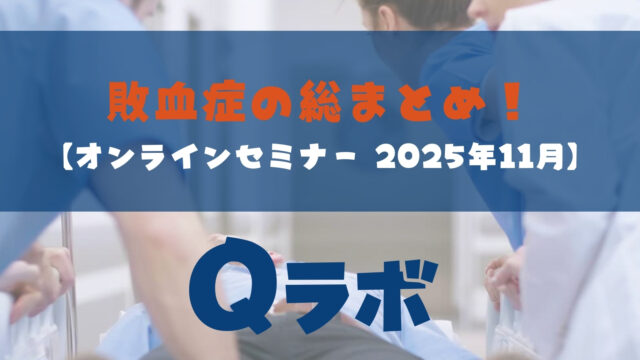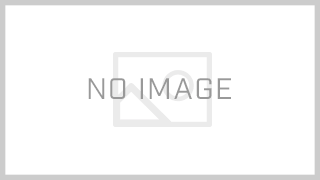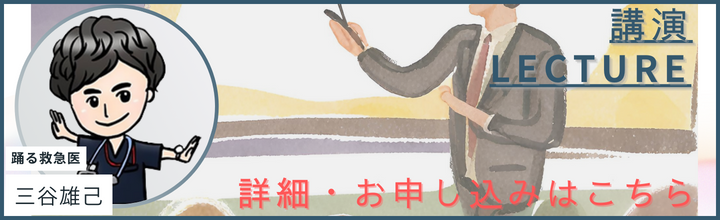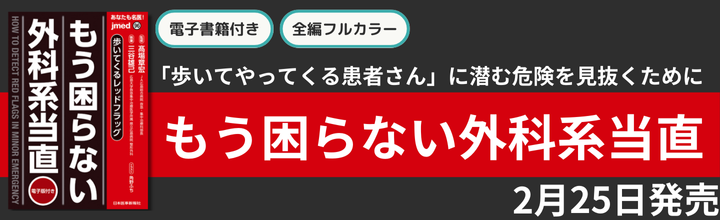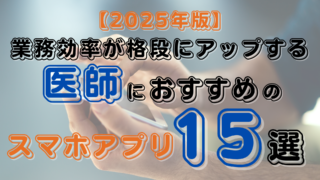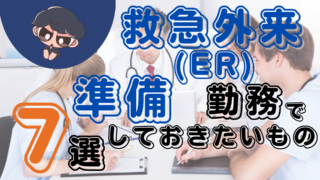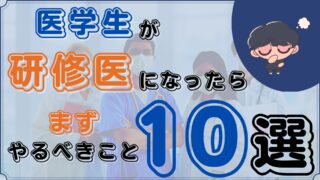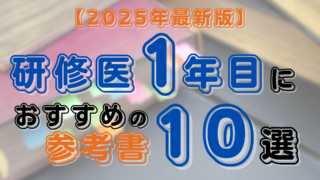小児心停止の判断:評価に立ち止まらない現場対応
「実際には、どの程度の時間、酸素投与および人工呼吸を実施しても心拍数が60回/分未満かつ循環不良である場合を、この条件に該当すると判断すべきでしょうか」— 救急救命士・r.sさん
広島県内で救急救命士として活動するr.sさんから、小児のプロトコールについて質問が寄せられました。
「十分な酸素投与と人工呼吸にもかかわらず」という表現が、現場でどう判断すべきか。
この疑問は、多くの救急救命士や医療従事者が抱えているものではないでしょうか。
今回のQラボでは、三谷がPLS2025(小児二次救命処置ガイドライン)を基に、
現場でどう動くべきかを丁寧に解説しました。一緒に学んでいきましょう。
プロトコールの「十分な」とは、どれくらい?
r.sさんが疑問に感じたのは、小児・乳児・新生児のプロトコールにある一文でした。
「十分な酸素投与と人工呼吸にもかかわらず、心拍数が60回/分未満で、かつ循環が悪い(皮膚蒼白、チアノーゼ等)の場合には胸骨圧迫を開始する」
この「十分な」という表現が、現場では迷いを生みます。30秒? 1分? それとも2分? 明確な時間が示されていないからこそ、判断に悩むんです。
r.sさんは、自分の所属本部の救急課にも確認しましたが、
地元MC(メディカルコントロール)に照会することなく独自に判断した回答で、明確な根拠が示されていないと感じたそうです。だからこそ、より医学的・実務的な観点からの見解を求めて、Qラボに質問を寄せてくれました。
結論:即座に胸骨圧迫を開始してよい
「結論から言うと、心拍数が60回/分未満で、かつ循環が悪い(皮膚蒼白、チアノーゼ等)の場合、即座に胸骨圧迫を開始するでよいと思いました」 — 三谷先生
「即座に」という言葉が、ここでは重要です。つまり、一定時間待つ必要はないということです。
PLS2025(小児二次救命処置ガイドライン2025)を基に、この判断の根拠を丁寧に説明していきます。
ガイドラインには「○秒待つ」とは書いていない
三谷先生が強調したのは、
ガイドラインには固定の待機時間が示されていないということです。
「小児ガイドラインPLS2025では、人工呼吸や酸素投与をトライするという『○秒』『○分』といった固定の待機時間は示されていません」 — 三谷先生
では、現場ではどう動けばいいのでしょうか。三谷先生は、判断の流れをこう整理してくれました。
「気道確保→高流量酸素下でのバッグ・マスク換気(BMV)をただちに開始し、心拍数が60回/分未満で、かつ循環が悪い(皮膚蒼白・チアノーゼなど)場合には、即座に胸骨圧迫を開始という運用になります」
バッグ・マスク換気(BMV)というのは、バッグとマスクを使って、手動で患者さんに呼吸を補助する方法です。救急の現場では、気道確保と同時にこのBMVを開始します。
そして、BMVを始めながら心拍数と循環の状態を評価し、心拍数が60回/分未満で循環不良なら、
その時点ですぐに胸骨圧迫を開始する。
「一定時間換気をしてから圧迫に移る」というような待機は求められていないんです。
ガイドラインの根拠を深掘りする
三谷先生は、PLS2025の該当箇所を引用しながら、現場での判断をさらに具体的に解説してくれました。
① 評価は10秒以内
「反応・呼吸・脈拍の評価は10秒以内とされており、判断に迷えばただちにCPRを開始します(p.16)」
現場では、
「評価のために立ち止まらない」ことが原則です。10秒以内に評価して、迷ったらすぐにCPR(心肺蘇生)を始める。これが、ガイドラインの基本的な考え方です。
② BMVを開始しつつ即判定
「『脈拍があるが呼吸がない』場合:気道確保+BMVを12〜20回/分で行い、約2分ごとに再評価(p.16-17)。『脈拍あり+HR<60/分+循環不全』の場合:CPRを開始(p.17)」
HR(Heart Rate)というのは、心拍数のことです。つまり、「脈拍はあるけれど、心拍数が60回/分未満で、かつ循環不全(皮膚蒼白やチアノーゼなど)」なら、BMVを始めた時点で胸骨圧迫を開始するということです。
③ 徐脈アルゴリズム(図2, p.35)
徐脈(じょみゃく)というのは、心拍数が異常に遅い状態のことです。ガイドラインには、徐脈への対応がフローチャートで示されています。
「気道確保+酸素下BMVを『ただちに』開始(Box2)→HR<60/分かを確認(Box3)→HR<60/分+心肺機能不全なら『ただちに胸骨圧迫』(Box4)」
ここでも、「何秒間BMVを行う」といった記載はありません。すべてが同時並行で進むんです。
④ PBLS総論(p.17-18)
PBLS(Pediatric Basic Life Support)というのは、小児の一次救命処置のことです。
「BMV準備が整い次第、30:2(救助者複数の場合は15:2)で圧迫と換気を併用。過換気は有害とされ、『胸が上がる程度』の換気量に留めます」
30:2というのは、胸骨圧迫30回に対して、人工呼吸2回という比率です。救助者が複数いる場合は、15:2になります。
また、過換気(かかんき)、つまり呼吸を入れすぎることは有害です。
胸が上がる程度の換気量に留めることが推奨されています。
現場での実際的なポイント
三谷先生は、現場対応を想定した実践的なポイントも示してくれました。
「私自身も現場対応を想定すると、気道確保と同時にBMVを始め、脈拍・皮膚色・反応性を並行して観察。『60回/分未満+チアノーゼ or 蒼白』なら、その時点で圧迫へという判断となるでしょう」 — 三谷先生
ここで大切なのは、
「並行して」という言葉です。
気道確保、BMV、脈拍の確認、皮膚色の観察。これらはすべて同時に進めます。一つ一つを順番にやっていたら、時間がかかりすぎてしまいます。
そして、「60回/分未満+チアノーゼ or 蒼白」という条件を満たしたら、その時点で胸骨圧迫を開始する。待つ必要はないんです。
なぜ「人工呼吸を試す」という表現なのか
三谷先生は、プロトコールの背景についても考察してくれました。
「完全に私の主観ですが、おそらく小児の心停止は呼吸原性が多いという背景から、このような人工呼吸や酸素投与を試すというプロトコルになっているのかもしれませんね」 — 三谷先生
呼吸原性(こきゅうげんせい)というのは、呼吸の問題が原因で心停止に至るということです。成人の心停止は、心臓の問題(心原性)が多いのに対し、小児では呼吸の問題から始まることが多いんです。
だからこそ、まずは気道確保とBMVで呼吸を改善させることが優先されます。
でも、それでも心拍数が60回/分未満で循環不良なら、すぐに胸骨圧迫を開始する。この流れが、小児救急の基本なんです。
最後に:プロトコールは各団体の判断に従う
最後にこう付け加えさせてください。
「これらはあくまでガイドラインと自分の判断や解釈なので、実際にプロトコルにそって救護にあたるかは必ずr.s様の団体のご判断に沿ってくださいね」 — 三谷先生
ガイドラインは、あくまで基本的な指針です。実際の現場では、各団体のプロトコールや、MCの指示に従うことが大切です。
r.sさんも、三谷先生の丁寧な説明に感謝の言葉を寄せてくれました。
「お忙しい中、詳細にご回答いただき誠にありがとうございます。ガイドラインの根拠や実際の判断の流れまで丁寧にご説明くださり、大変勉強になりました。『評価に立ち止まらない』『BMVと同時並行での判断』という実践的な視点は、現場での判断の軸として非常に参考になります」 — r.sさん
今回のディスカッションから学べること
- 「○秒待つ」という固定の時間はない。気道確保とBMVを開始しながら、同時並行で評価する
- 「評価に立ち止まらない」ことが原則。10秒以内に評価し、迷ったらすぐにCPRを開始
- 心拍数60回/分未満+循環不良なら、即座に胸骨圧迫を開始してよい
- 小児の心停止は呼吸原性が多いため、まずは気道確保とBMVが優先される
- ガイドラインは指針、現場では各団体のプロトコールに従う
疑問を共有することの大切さ
今回のr.sさんの質問は、多くの救急救命士や医療従事者が抱えている疑問だったのではないでしょうか。プロトコールに書かれている「十分な」という表現は、具体的な時間が示されていないからこそ、現場では迷いを生みます。
でも、今回のディスカッションを通じて、
「即座に判断してよい」ということが明確になりました。気道確保とBMVを開始しながら、心拍数と循環の状態を並行して評価する。そして、条件を満たしたら、その時点で胸骨圧迫を開始する。
疑問を持ったら、一人で悩まずに、Qラボで共有してみませんか。きっと、誰かが一緒に考えてくれます。そして、その答えは、あなただけでなく、同じ疑問を持っている他の仲間にとっても、大きな学びになるはずです。
あなたは、現場でどんな疑問を抱えていますか。迷ったこと、判断に悩んだこと、ぜひQラボで共有してください。一緒に、学んでいきましょう。