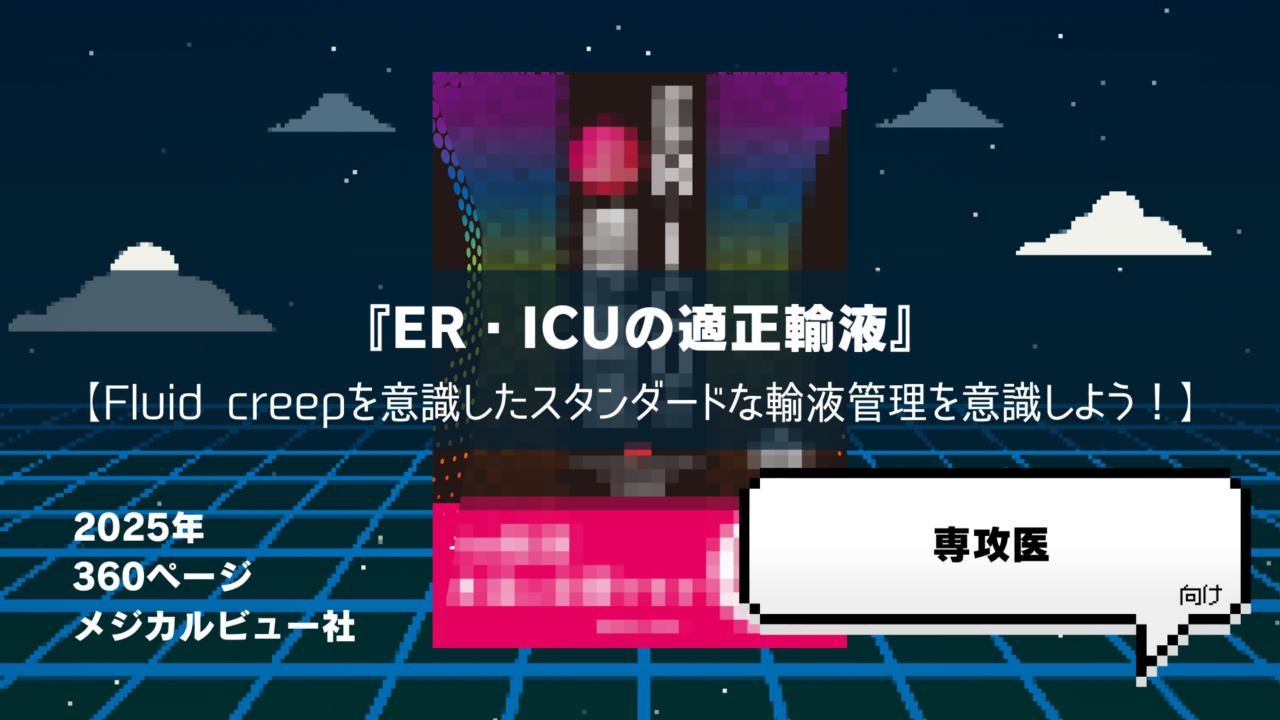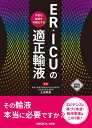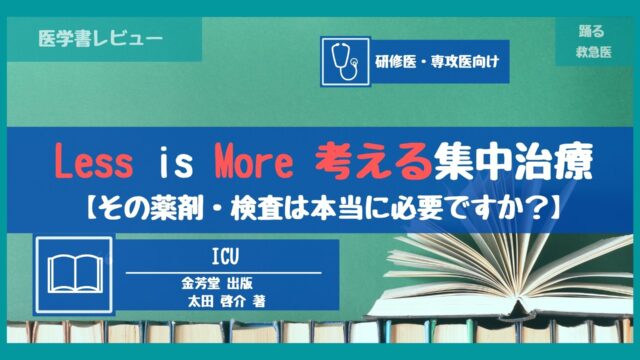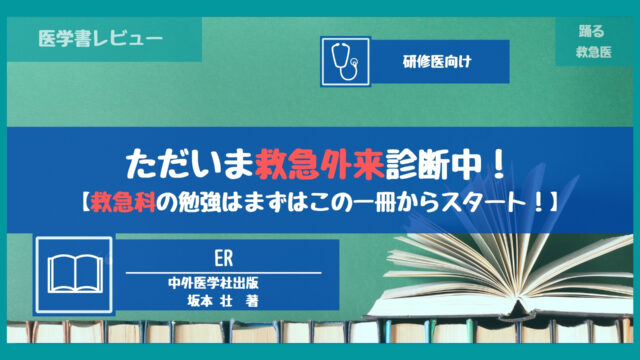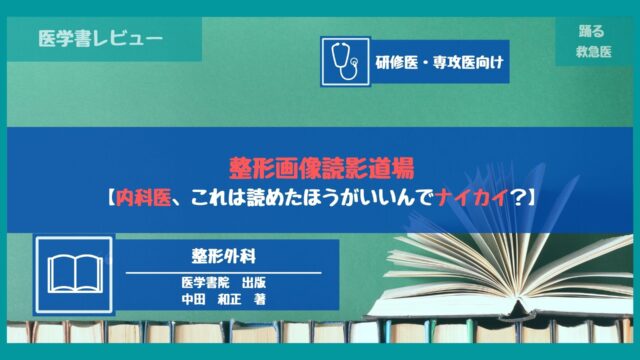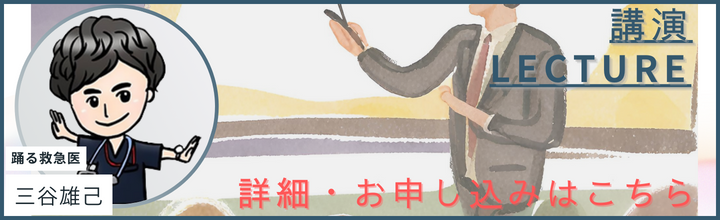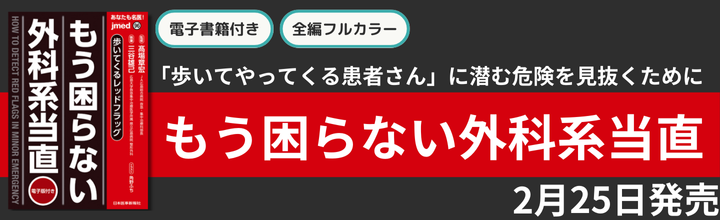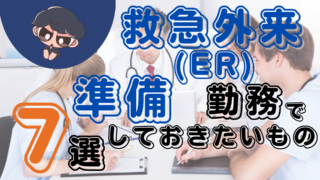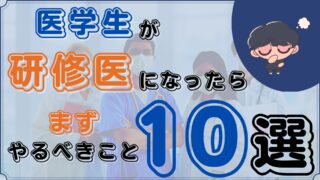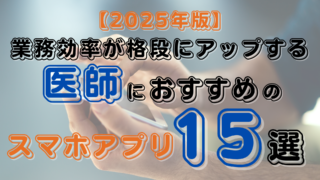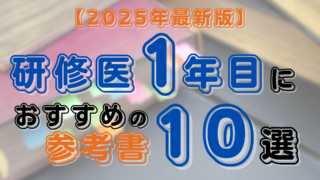そんな“Fluid creep”に気づいていますか?
近年、救急やICU領域では過剰輸液を避けるトレンドが注目される一方、実際には「輸液が静脈ラインや薬剤投与用などで、どんどん積み重なってしまう」という問題に直面しがち。これがいわゆる“Fluid creep(フルイドクリープ)”です。
本書は輸液療法の基礎理論から疾患別の具体的な輸液戦略、そして過剰輸液をいかに防ぐかを体系的に提示してくれます。
出版社の方のご厚意でご贈呈いただいた本書でしたが、救急医・集中治療医としてとても唸る一冊でした…!
医師や医療従事者が日々感じている
「急性膵炎のときは、結局どの程度の輸液量が最適なのだろう?」
「肺塞栓やARDS症例での細かな調整はどうしているのか?」
といった疑問を解消したい方に、ぜひおすすめしたい一冊です。
救急科・集中治療科で臨床経験を積み、輸液管理に関する疑問を常に抱えてきた医師です。
海外のFluid Stewardshipの概念を学ぶ中で、「日本でも実践できる具体的な輸液削減モデルが知りたい!」という思いから、輸液管理本を多数読み漁ってきました。本書を実際に読んだところ、「やはりFluid creepを可視化し、意識して管理する大切さ」を改めて痛感しました。この記事では、私の体験談も交えながら、皆さんの臨床の一助となる情報をお伝えします。
1.本書のターゲット層と読了時間
・救急科・集中治療科を中心とする医師や看護師、薬剤師など、輸液管理に関わる医療従事者
・研修医や専攻医、そしてICU管理を学び始めたばかりの若手~中堅スタッフ【推定読了時間】
・約6~8時間(360ページのため、人によってはもう少し時間がかかる場合も)
B5判に近いサイズで360ページと比較的ボリュームがありますが、写真や図解、症例ベースの解説が多いので、想像以上に読みやすい印象です。
休日や夜勤明けのまとまった時間を使えば、1~2日で一気に読み進められそうです。
2.本書の特徴
1. Fluid creep(忍び寄る輸液)を中心概念として徹底解説
2. 欧州で広がるFluid Stewardship構築の流れを紹介
3. 急性期生理学・体液組成から各種疾患の輸液反応性評価まで網羅
4. 症例ベースで具体的な輸液量・薬剤投与量を可視化
5. 最終章の“in/outの振り返り”が臨床現場への応用に直結
本書の最大の魅力は、やはり「Fluid creepをいかに減らすか」にフォーカスしている点です。点滴ライン確保や薬剤投与など、つい漫然と追加してしまう輸液が実は大きな蓄積になっていることを強く意識させてくれます。
さらに、敗血症や外傷、呼吸器疾患や心不全など、多彩な疾患における輸液管理を章立てでわかりやすく整理。特に第4章では、「ROSEモデル」と呼ばれる輸液適正化のフレームワークを症例ごとに当てはめ、日数・目的別にどんな点滴や薬剤をどれくらい投与しているかが克明に記載されているのが画期的です。
3.個人的総評
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
必要性については、「輸液制限や適正輸液を意識している人」にとっては必須ですが、まだそこまで深く考えていない人には刺さる度合いがやや限定的かもしれません。
一方、継続使用度は間違いなく高いと感じました。実際にICUや救急外来で患者さんを受け持つたびに、「あの症例の1日目はこうしていたよな…」と何度も振り返りたくなる構成です。
本書は“雑学”や“読み物”というよりは、実際の臨床に直結するマニュアル的な使い方ができる一冊。症例数も多いので、「こういう場合はどう投与量を調整したらいい?」という問いにすぐ答えが見つかるのがポイントです。
ただし、“面白さ”の点は3.0とやや控えめにしました。これは、あくまで専門的で実践重視な内容のため、エンタメ感やポップさを求める方には地味に映るかもしれません。しかし、臨床のリアルな悩みを解決したい方にとっては逆にその実直さが魅力になるはずです。
4.おすすめの使い方・読み進め方
・ざっと全体を通読し、Fluid creepに対する認識をアップデート
・担当患者さんの病態・疾患と似たケースを拾い読み
・RoSEモデルを使って、自分の症例のin/outを記録・分析
・ICUや病棟カンファレンスでのディスカッションツールに
・薬剤別・目的別の輸液量チェックリストとして活用
特に、「症例が似ているから、この日の投与量や薬剤選択を参考にしよう!」という辞書的な使い方がおすすめです。
また、自施設で発生しているFluid creepを可視化するために、本書にあるテンプレートや考え方を取り入れてみると効果的です。かなり時間はかかってしまうかもしれませんが…汗
多職種カンファレンスで本書の内容を共有するのも良いでしょう。看護師さんや薬剤師さんと一緒に、「不要な輸液が増えないように薬剤投与ラインをどう調整するか」などを話し合うきっかけになります。
5.まとめ
本書は、Fluid creepを意識した輸液管理の新たなスタンダードを理解するのにおすすめの一冊である。
本書は、ICUでの輸液量をどうコントロールするか?という切実な問いに対して、欧州での取り組みから得たアイデアを踏まえ、具体的な輸液適正化モデルを提示してくれます。
「ERや集中治療で患者を診る際、過剰輸液が本当に危険だと頭ではわかっているが、実際の運用方法がわからない…」という方には特に必読の内容。
症例を読むたびに、いかにFluid creepが発生しやすいかに気づかされ、日々の診療でも「これ以上の輸液は必要か?」と立ち止まって考える習慣が身につくはずです。
ぜひ多職種で共有しながら、Fluid creepを減らすためのアイデアを膨らませてみてください。
タイトル:ER・ICUの適正輸液
著者:土谷 飛鳥 (編集)
出版社:メジカルビュー社
発行年月日:2025/3/3
ページ数:360ページ
必要性:
本の薄さ:
わかりやすさ:
面白さ:
継続使用度:
オススメ度:
重症患者の救命率アップや合併症削減のためにも、「Fluid creepを防ぎ、不要な輸液を避ける」という概念をぜひ本書で学んでみてください。
この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は
今後も定期的に記事を更新していきますので
各種SNSの登録よろしくお願いいたします!
【公式ラインアカウント】
各種SNSでのコンテンツ配信を定期的に配信!
この中でしか見られない限定動画配信もしています◎
日々のスキマ時間に気軽に見ることができるので、興味があれば是非登録していただければ幸いです!
コチラのボタンをタップ!👇
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!